創刊号 (2002年9月) ISSN 1347-7587
創刊号 (2002年9月) ISSN 1347-7587
すべての組織体がそうであるように、私たちの学会もまた時代の要請がもたらした果実だといってよい。
直接のきっかけは『講座・日本歴史』第三版の最初の執筆者会議にあった。志を同じくする各地の専門家諸氏にも声をかけ会合を持ったのが昨年5月。以後会を重ね、輪を広げながら確認し続けたのが「今なぜ学会なのか」の答えだ。私たちの志は次の一点に集約されていたといってよい。
冷戦終結後、外なるグローバル化と内なる保守化の流れの中で「平和と民主主義」が狭小化され続ける時代への憂慮である。その流れが「第二の敗戦」と重なり、負債が限りなく民草に押しつけられ、しかも「敗戦」がことごとく私たちの生きてきた戦後史見直しの動き-と知の衰退-と連動し合っている。
いったい今歴史家は何をなすべきか。知の復権のため、戦後史見直しの逆走にどう対処して、新しい時代を切り拓いていくべきなのか。志を具現化する道である。
第一に、グローバルな視座の中で、個々の専門領域を越え、国境の壁を払って戦後史を位置づけ直すこと。第二に、権力や大国の高みからでなく、同時代に生を享け、共に生きた市井の目線に立って時代を読み解くこと。第三に、従来の学会ギルド集団の弊から脱し、同時代の志を同じくする市民にも開かれた知的共同体をつくり上げること。
私たちが、一国歴史主義を彷彿させる“戦後史”でなく“同時代史”を冠称するゆえんである。思想的位相でナショナリストとされながら“知の権力”の道を拒み市井の目線にこだわり続けた三宅雪嶺を想起することもできる。
すべての組織体がそうであるように私たちの学会もまた、生成発展のためには、異質で若い変革のエネルギーを求め続けるだろう。そしてそれこそが、時代の要請に応えて果実を豊かに稔らせる道であるはずだ。
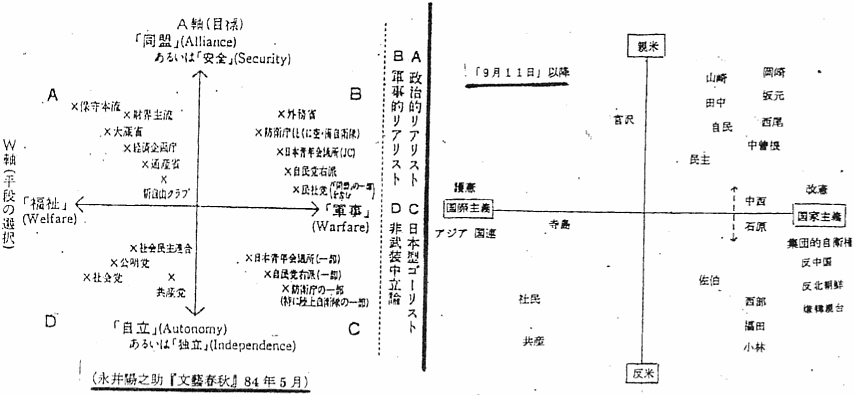
安保条約をめぐる今日の政治的・イデオロギー的状況を捉えるうえで、84年に永井陽之助の行った分析はきわめて興味深い。図のように彼は安全と自立を縦軸に、福祉と軍事を横軸にマトリックスを描くことによって、リアリストを政治重視と軍事偏重に峻別する一方、日本型ゴーリストと非武装中立を対極に位置づけた。彼は保守本流を担う政治的リアリズムの核心を吉田ドクトリンに求め、それを戦後日本の「平和の公共哲学」と位置づけ、米国との軍事協力の拡大を求める軍事的リアリストと一線を画す必要性を強調した。
以来18年、冷戦の終焉、湾岸戦争、そして何よりも昨年の「9月11日」を経て、状況は大きく変化した。筆者は便宜的に、親米と反米を縦軸に、国家主義と国際主義を横軸としたマトリックスを描いたが、今や憲法を改正し集団的自衛権に踏み切り、国際協力という名の対米軍事協力を強化せよという勢力が政界や論壇のレベルで大きな発言権を持つに至り、保守本流はその影を薄くした。とはいえ注目すべきは、国家主義的な改憲勢力において、「教科書の会」の分裂に見られるように、親米派と反米派の対立が顕著になってきたことである。後述するように、渦中の石原慎太郎は両派の間を巧みに動き回る存在と言えよう。他方で明らかなことは、護憲勢力が世論を獲得していくためには、安保条約に代わる代替構想を具体的に提起せねばならない、ということである。
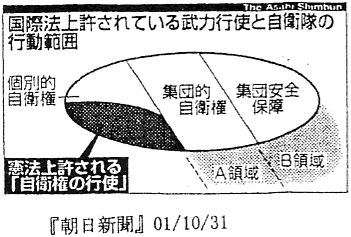
周辺事態法やテロ特措法に基づく日本の対米軍事協力は図のA領域に示されるように集団的自衛権の境界を踏み越える限界に迫るものである。(ちなみにB領域は多国籍軍への支援)とはいえ小泉政権にあっても公式には、集団的自衛権は保持しているがその行使は憲法上許されない、という従来の政府解釈を維持している。
これに対し、佐瀬昌盛は近著(「『集団的自衛権』PHP新書)で、そもそも旧安保条約は当時の西村条約局長が言うように「日米間で集団的自衛の関係を確立していく」という前提で成立したものであった以上、右の政府解釈は誤っており、従ってそれを「是正」することで直ちに集団的自衛権に踏み込むことが出来ると主張する。歴史的経緯が十分把握されていない場合には、きわめて説得力をもった議論のようである。
一 実はこの問題は拙著『安保条約の成立』(岩波新書)で扱った中心テーマの1つである。その際、82年に公開されたが数多くの削除があった外務省資料の原文のコピー(堂場文書)を活用した。ちなみに、昨年10月に外務省は同資料の全面公開に踏みきったが、前代未聞の「二重公開」の理由は説明されていない。さて、これら新たな資料から明らかになってきたことは、西村が「集団的自衛の関係の確立」を言う場合、それは何よりも、憲法9条をクリアーしつつ独立後も日本に駐留する米軍の「法的基礎」をいかに説明するかという問題に関わっていた、ということである。
当初は国連決議に根拠を求めようとしたが、やがて冷戦の現実を踏まえて、日本の基地提供と米軍による日本防衛という「五分五分の論理」が対米交渉の機軸にすえられた。これこそ西村の言う「集団的自衛の関係」の論理であって、しかも注意されるべきは、日本側の集団的自衛権の行使とは、上の図のA領域にあたる基地提供に限られている、ということである。そもそも、佐瀬が求める海外派兵としての集団的自衛権は54年の自衛隊発足以来、明確に違憲とされてきたのであって、ここが混同されてはならない。
二 さて、51年の日米交渉では米側に押し切られて「五分五分の論理」どころか、日本には基地提供義務があるが米側には日本防衛義務がないという、無条件的な全土基地提供条約に結果してしまい、右の「論理」が達成されたのは、ようやく60年の安保改定によってであった。こういう結果を招いた背景を考えるためには、日米交渉の焦点が何であったか、という問題から再検討せねばならない。高坂正堯『宰相吉田茂論』に代表される通説では、再軍備問題こそが焦点であったとするが、日米資料の詳細な検討から明らかになることは、米側の最大の獲得目標は占領期と同じ全土基地、自由使用の確保にあったのであり、これこそ、今日に至るまでの安保条約の本質問題に他ならないのである。
吉田首相や外務省がこうした植民地的な要求に対抗できる手段としては、米側にとって死活的な基地提供を逆に最大の切り札として活用することであった。しかし、パワーポリティクスの感覚を持つはずの吉田は早い段階でそれを放棄してしまった。その背景として拙著では、共産主義の脅威から天皇制を守るために無条件的な米軍の駐留を求めた昭和天皇による、政府やマッカーサーを飛び越えた「二重外交」という問題の重大さを提起した。
一 憲法調査会が設置され、9条改正を含む憲法改正議論が進み、世論調査においても改正支持が相対多数を占める状況である。ここ10年来のこうした世論状況の大きな変化とブッシュ政権の圧力を背景に政権側は、海外派兵という集団的自衛権の本体に踏み込む機会をねらっているようである。しかし強調されるべきは、国連憲章51条が規定する集団的自衛権発動の前提条件は「領域への武力攻撃の発生」であって、安保条約の極東条項や周辺事態法にあるような、一般的な平和への脅威とか攻撃の恐れでは憲章の求める要件とはならず、それはいわば「米国的自衛権」に他ならない、ということである。
二 とはいえ、集団的自衛権と改憲を公然と主張する石原慎太郎を推す「首相待望論」が高まっていることは否定できない。そこには、かつて彼が『ノーと言える日本』において反米的で米国に直言するスタンスをとったことが少なからぬ影響を及ぼしているようである。しかし彼の本質は親共和党政権、親台湾であり、何より明確なことは反中国である、ということである。だからこそ彼は、中国と対決するときに米国が日本を守ってくれるか否かに最大の関心を払っているのである。つまり、彼の反米姿勢はあくまでも「米国の掌」の上においてであって、冒頭で彼が反米と親米の間を巧みに動いていると述べたことの意味はここにあるのである。
永井は吉田ドクトリンを「平和の公共哲学」と位置づけたが、この路線の大きな欠陥は「アジア外交の不在」であった。石原や軍事的リアリストの路線も、中国や韓国への嫌悪感を背景にしたもので、それは必然的にアジアにおける日本の外交的な孤立と、さらなる米国への軍事的な過度の依存を招くであろう。それはまた、日本の頭越しに米国が中国と「取引」するという、かの71年の「ニクソン・ショック」がいつでも再現される恐れを抱えこんでいる、ということである。
三 以上の“袋小路”を見据えつついわゆる護憲派は、別の外交的な選択肢を提起するという困難な課題に挑戦していかねばならない。具体的には、「スポークス・システム」といわれる、アジアにおける米国を中心とした二国間同盟の枠組みを乗り越える方向をいかに構想するか、ということである。その際、軍事的リアリストが強調する日米韓軍事協力の強化論と、それに対する日中韓3国の提携強化論という対極の議論において、日韓関係が結節点になっていることに注目したい。戦後日本の民主主義総体が問題とされる「ビンの蓋」論を実体において克服することに努めると共に、「同じ価値観」を共有できるはずの日韓のあり方を根本的に改善していくことで、やがて「不戦関係」をアジアと周辺諸国に拡大していくという方向性を展望したい。
「日米経済協力」構想とは、朝鮮戦争下の1951年から52年に日本政府、財界、GHQ/SCAPなどが唱えた、アメリカの軍需産業動員への日本の協力体制のことです。しかし、日米両国が共同で具体的プランを作成したことはなく、その内容は終始曖昧でした。
山本満氏は、「日米経済協力」構想は、「計画、期待、思惑、幻想、スローガン、あるいはそれらすべての混合物」であり、発想はその後の日米関係に影響を与えたが、具体的内容に乏しかったとしました。これに対し中村隆英氏は、この構想は日本をアメリカの陣営に引き止めるための「特需」継続計画であり、講和後の1952、53年に「特需」が増大したことを根拠に、実体があったと述べました。いわば、山本氏の「まぼろし説」と、中村氏の「実在説」が対立しているわけです。
よく知られているのは、1951年1月29日の吉田、ダレスと、マッカーサーとの会見です。ダレスから再軍備を求められたのに対し、吉田が「再軍備は日本の自立経済を不能にする」と抵抗し、マッカーサーが、日本は「軍事生産力」で「自由世界」に貢献できると、両者の間をとりなしたとされます。印象的なエピソードではありますが、「日米経済協力」構想がこの会談から生まれたわけではありません。
アメリカが、日本を軍需生産のために本格的に動員しようとした契機は、1950年10月の中国人民義勇軍の参戦です。1951年2月、アメリカ政府調達局は、日本を太平洋地域の米軍のための軍需物資・兵器の調達先、東南アジアで展開するアメリカの軍事援助計画の補佐役にしようと、GHQ/SCAPに対し、日本の工業動員力の調査を依頼しました。これを受けて、いわゆる「トップレベル作業」(最高生産能力調査)が実施されました。
日本側は、「経済自立」の切り札になると、この構想を歓迎しました。日本は、講和後、政治的独立を回復した際、果たして経済的自立ができるかという問題に直面していた。経済自立とは、特需や経済援助に頼らない経済ということです。日本政府は、早期の経済自立は不可能であり、講和後も当面は、経済援助・特需によって凌ぐしかないと考えました。ところが、アメリカ政府は占領終結を待たずして、対日援助打ち切りの方針を固めます。
こうした折に、「日米経済協力」構想がアメリカ側から提起され、日本側は、朝鮮特需後の「新特需」に期待をかけました。「新特需」とは、アメリカがその軍備計画にもとづいて軍需物資を計画的に調達すること、つまり、日本が「アジアの兵器廠」となることです。その後、朝鮮戦争への動員からポスト講和体制の問題に重点が移りました。アメリカ側は、「日本経済協力」を、講和後の安全保障上の問題として捉え直します。
しかし、アメリカの対日政策担当者の影響力には限界があり、選択肢は限られていました。1951年のMSA法により、アメリカの対外援助の重点は経済援助から軍事援助に移り、1953年に成立したアイゼンハワー政権は、「援助でなく貿易を」(trade not aid)をスローガンに掲げました。アメリカ政府の日本担当者は、経済援助・政治借款は実現不可能だが、MSA計画のもとでの軍需物資の調達という形の援助ならば可能だと考えました。
1952年3月、占領終結に先立ち、GHQ/SCAPは兵器生産の再開を許可し、本格的な兵器特需が始まりました。1953年4月、国務省は、少なくとも2年間は同じ水準の特需を行なうとの声明を出します。また、同年秋のMSA交渉においては、アメリカ側は経済援助を拒否したものの、1億ドルの日本の「域外調達」は約束しました。
「アジアの兵器廠」日本という構想は実現したのでしょうか?1952年、53年の特需は、朝鮮戦争が激しかった時期期を上回り、8億ドルにも達しました。1952、53年の輸出は12億ドル台でるから、特需がいかに多額のドルを稼いだのかがわかります。特需の増加のなかには、占領経費の半額ドル払い(アメリカ側負担)が含まれます。在日米軍の維持費を日本国民が負担する「防衛分担金」は、旧安保条約の従属性の象徴でしたが、アメリカ側は、ガリオア援助に代る経済援助と位置付けていました。
在日米軍のドルによる調達が増える一方で、当初の構想にあった、アジア地域の軍需物資を日本から調達する構想(「域外調達」)の方は、ほとんど実現しませんでした。アメリカ政府は、対外援助は軍事援助に限定するという原則を掲げていましたが、実際には、「域外調達」という形で、先進国に経済援助を行なっていました。しかし、日本は、MSA資金による「域外調達」の恩恵をあまり受けなかったのです。
以上の結論は、1952年~53年にかけて、日本経済は基地経済化の傾向を強めたものの、「アジアの兵器廠」にはならなかったということです。
「軽武装・経済優先」路線の「吉田ドクトリン」のうち、「軽武装」については、多くの疑問が出されていますが、「経済優先」の神話の方はまだ健在です。下田武三は、上記の吉田・ダレス会談で、日本は経済で「自由世界」に貢献すると、吉田がいい切ったときに経済的繁栄の道が選択されたと述べています。こうした見方が広く受け入れられていることには首を傾げざるを得ません。もし、軍事生産力を持って「自由世界」に貢献していたならば、兵器輸出大国日本が出現していたのではないでしょうか。私が語るまでもなく、半世紀前の有沢広巳の言葉を思い出せば充分でしょう。
日米経済協力構想のもう1つの柱は、東南アジア開発でした。当時の「東南アジア」とは、共産圏をのぞく東アジア、東南アジア、南アジアを含む広い地域概念です。
日本が工業製品を東南アジアに輸出し、東南アジアから原材料を輸入するプランは、すでに朝鮮戦争前に、冷戦の開始ともにアメリカ政府やGHQ/SCAPが考えた日本経済復興プランの一部でした。その目的は、中国市場の代わりに東南アジア市場を日本に確保すること、アメリカからの原材料輸入を減らしてドル不足を緩和することにありました。これは、日本を「アジアの工場」にする構想ですが、この構想が、「日米経済協力」構想において、「アジアの兵器廠」構想と結びついたわけです。
アジアに対する日本の政策は、どうだったのでしょうか?「外交と金融はその性質を同じうする。いずれもクレジット(信用)を基礎とする」という吉田茂の言葉は有名ですが、吉田が優先したのは欧米に対する信用でした。吉田は、欧米から金を借りるためには、まず借金を返すことだと、戦前外債の償還を優先しました。これとは対照的に賠償については、「日本が支払うべき賠償の額は日本の支払能力によって決定さるべきであって、求償国の蒙った損害及び苦痛の額によって決定さるべきものではない」と消極的でした。東南アジア貿易の拡大を図るためには、賠償問題を解決しなければならないと気づいて、吉田内閣が賠償問題に積極的になるのは、1953年6月頃からです。
ところで、「アジアの工場」構想は、実現を見たのでしょうか? ウィリアム・ボーデンは、 The Pacific Alliance の第5章を、「実現された工場 - MSAと日本」と題し、日本を中心としたアジアの垂直的分業関係が1950年代半ばに成立したとしています。しかし、1950年代半ばに日本がアジアの工場になったと見るのは疑問です。東南アジア貿易が1950年代初めを頂点に、その後、1950年代を通じて大幅に比率が下がっています。
東南アジア貿易が拡大しなかった原因としては、一次産品価格が下落し、東南アジア地域の購買力が低下したこと、ポンド圏が第2次大戦後に、強化されたことが挙げられます。当時、東南アジアの広汎な地域はポンド圏に属しており、ポンド圏諸地域の貿易制限政策は、日本の輸出拡大を妨げました。
1950年代の東南アジアの国際分業を、日本中心に垂直的経済統合を図ろうとしたアメリカ・日本と、それに抵抗するアジア諸国という二元的対立の構図で描くのは、過度の単純化だと思います。まず、アメリカの東南アジアに対する影響力には限界がありました。また、アメリカは中ソの影響力を食い止めるため、イギリスやフランスの植民地体制維持を認めました。日本にとって東南アジアの原料が必要なように、西欧諸国にとっても旧植民地・植民地を含む経済圏の確保が経済自立の条件と考えられました。こうして、ヨーロッパの旧植民地地域の市場においては、日本とヨーロッパとが競合することになったのです。
「アジアの兵器廠」をめざした路線は、ごく短期間に終わりました。1955年には、特需抜きで国際収支均衡が一応達成されます。
「新特需」や兵器生産拡大に対しては、批判的・懐疑的な見方が広範にありました。政府、財界、政界が、こぞって兵器生産の復興を歓迎したかのように見えますが、必ずしも、そうではありません。懐疑論が強かったのは、経済成長への別の道が見えていたからだと思います。投資主導型の高度成長の起点に、1951年~52年の消費ブームがありました。「朝鮮特需」により、1951年に鉱工業生産が戦前水準を回復した後、1951~52年に「消費景気」が起きます。1952年には、消費支出は年間16%という高い伸び率を示しました。とくに農村の消費水準の上昇は著しく、1952年には戦前水準を2割も上回りました。
農村の消費水準上昇は、農地改革による小作料負担の軽減と、所得分配の平準化がもたらしたものです。ドッジラインの後は、租税負担も軽減され、農家に経済的余裕が生まれました。同時に、この時期の農家所得の増大は、農外収入の増大による部分が大きかったのです。農外収入増大の要因の1つは、農業関連の公共事業の拡大だと推測できます。1951年~53年に、議員立法により、「積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法」(略称「積寒法」)をはじめ、土地改良のための法律が次々に制定され、土地改良事業費が飛躍的に伸びました。
前者は、占領期の経済改革の成果と言えましょう。また、後者は、ドッジという重石がなくなった後に形成された利益政治だと言えましょう。政党政治家の政界復帰とあいまって、本格的な政党政治が再開され、経済自立を背景に、ナショナリズムが強まり、吉田路線は一定の修正を加えられました。しかし、それはあくまでも、日米安保と「日米経済協力」構想において形成された外交的・軍事的な依存関係を前提としたものでありました。
今年は沖縄復帰30年にあたるが、「憲法は沖縄を排除してできたものではないか」というのが沖縄からの問いとして存在する。
「吉田ドクトリン」は正しかったのか、という点について。吉田は「基地の自由使用」というカードをうまく使えなかったのではないか。また、吉田は再軍備に抵抗したというのは事実だが、再軍備を抑制したのは内発的な要素だけではなかったのではないか。
「安保ただ乗り論」について。基地提供自体がすでに日本にとっては大きな譲歩である。また日米安保はモノとヒトとの非対象な交換であり、その意味で日本はすでに十分な貢献をしている。「ただ乗り論」は誤りである。
戦後日本には「アジア外交」が不在・欠落したというより「アジア外交の戦略的・積極的否定」が存在したが、それは冷戦の論理によって生み出された、日米基軸による日本の再生、という戦略と、日本のナショナリズムからくるアジア軽視が存在したためではないか。それは、とくに韓国との交渉過程で日本が見せたエモーショナルなまでの拒絶反応に現れているし、それはまた政策決定者だけでなく大衆レベルまで根深く存在したと思われる。新しいアジア外交を構想するにあたっては、サンフランシスコ講和・日米安保が、同盟関係としては例外的に長く続いた理由を考える必要がある。また、韓国などにも「日米安保によって日本を封じ込める」という発想(「ビンのふた」論)が存在しているが、このことは韓国外交のアメリカへの依存、という問題があることを示している。さらに、90年代半ば移行、アメリカの戦略から「中国脅威論」が台頭してきたことによって、東アジアの自発的な秩序構想が弱化してきたという問題もある。
日本がアメリカの兵器廠にならなかった理由としては、50年代に冷戦自体が政治経済的なものへと変質した(54年が転換点)ということがあったのではないか。
「国民感情」が重要。しかし「国民感情」とは何か。それについて考えるために、「逆コース」の文化現象学と、大衆ナショナリズムについて考察する必要があり、そのためには当時の50年代の流行歌や映画などを細かく見ていくことが必要である。ちなみに、当時の映画に見られる「戦後民主主義」のイメージとは「のびのびとやすっぽく、さわやかで軽薄」といったものであった。また同じ大衆ナショナリズムといっても、振幅と層があった。
(※なおコメントを文章化したものに、安田常雄「大衆文化のなかの『逆コース』」『評論』No.132、日本経済評論社、2002年8月がある)
「憲法は沖縄を排除してきた」ということについて。稲嶺県政の「沖縄イニシアティブ」は、沖縄が被害者意識を払拭してパワーポリティクスの中に位置付けられるべきだというものだが、これは、本土から30年遅れでやってきた「リアリズム」だ。
アジア外交について。新史料によって、吉田の対中国政策が予想以上に厳しく、「中共政権の打倒」まで視野に入れていたことが明らかになった。
吉田のリーダーシップは巷間言われているほどには存在しなかった。
アメリカには、54年より前からすでに日本を兵器廠にという意図は存在しなかった。
Q:アジアへの補償問題について、日本の民衆レベルのナショナリズムという点、日本の民主主義の未成熟という点から考えるべきか。
A(安田):1960年代前半からようやくアジアへの加害ということが民衆レベルで問題になりはじめる。50年代にはまだ問題にもならない。民主主義の未成熟という問題については今後の課題である。
Q:51年日米交渉の焦点はやはり再軍備問題だったのではないか。
A(豊下):再軍備問題が重要ではなかったとは考えていない。しかし「全土基地化・自由使用」の獲得こそが、アメリカの最大の目標だった。
Q:冷戦期には日本の選択の幅は狭かったが、冷戦後、東アジアの安全保障体制をどうつくるか、アメリカという政治的現実とどうつきあうのかが新しい課題として生じてきた。日本はどうすべきか。
A(豊下):冷戦後に選択肢が増えた中でも、日本外交はアメリカに縛られ続けてきた。ドイツの当方外交、韓国の北方外交と対照的である。
Q:サンフランシスコ講和でも日本人は「独立」を祝うわけでもなく、「独立」という自覚もなかったようだ。また基地の存在も問題にしない。こうした日本人の特質は、日本外交にどう影響したか。
A(豊下):吉田は、講和会議の全権への就任を最後までしぶっていた。そこには安保への抵抗感があったようだ。
A(安田):沖縄や基地周辺の人々を除くと、多くの人に占領感覚が稀薄だった。占領の「屈辱感」といった感覚については、50年代半ばからようやくとらえ直しがはじまる。
Q:50年代前半に南北朝鮮と国交を回復できた可能性はあったか。
A(豊下):50年代前半には吉田をはじめとして日本側の朝鮮・韓国蔑視は激しかった。
A(李):50年代半ばに、日ソ・日中には関係改善の動きがあった。そういう意味でひとつの機会ではあったのに、朝鮮については目に見える動きがあまりない。朝鮮半島にアプローチをかけるメリットが少ないと考えていたのかもしれない。どういう地域システムをつくるかという発想もない。
Q:「沖縄イニシアティブ」をどう考えるか。
A(外岡):「これまで50年間沖縄が1度でもイニシアティブをとったことがあるか」「また(経済振興という)アメとムチで基地との共存を強いられるだけではないか」という反感が沖縄にはある。本土の方が、分断・基地の歴史を考えない限り、新しい沖縄統治のイデオロギーとなるだけだろう。
Q:50年代の自立的な経済政策とはどのようなものだったのか。
A(浅井):「輸出振興」政策が確立するのは53~4年。それまでは特需依存だった。経済自立の画期は55年。
「同時代史学会」創立準備大会記念のシンポジウムでは、豊下楢彦関西学院大学教授「安保条約の原点と現点」、浅井良夫成城大学教授「『日米経済協力』構想と経済自立」の2本の報告がなされ、「外交の視点から」朝日新聞の外岡秀俊さん、「アジアの視点」から立教大学の李鐘元さん、「文化の視点から」電気通信大学の安田常雄さんのコメントがありました。
報告者のご両人は私の存じあげている方で、興味ある話をうかがわせていただきました。私の専門からすれば豊下報告の方になじみがありましたが、専門ではない方のお話を伺うことで視野を広げるということも、このような学際的な学会のメリットだと言えるでしょう。
この日は、サンフランシスコ条約・旧安保条約発効50周年の前日に当たります。この日のシンポジウムの表題が「サンフランシスコ講和50周年を考える」とされたのは、そのためでしょう。また、武力攻撃事態法案など有事関連3法案が国会に提出されたということもあって、大変タイムリーな企画だったといえます。安保体制はこのときから始まっているわけですから……。
この日の報告で私の印象に残ったのは、サンフランシスコ講和会議に出席した吉田首相が直前まで出席を渋っていたこと、それまでの日米交渉の中心的なポイントは日本の再軍備ではなく、駐留米軍への基地提供問題だったこと、しかし、これについては早々と決着してしまい、吉田首相は交渉カードとして利用した形跡がないことなどでした。いずれも豊下報告で指摘された点です。つまり、安保体制の出発から、米軍がいかに日本を利用するかが最大のポイントだったということになります。占領時代と同様の地位が米軍に保障され、それに日本が協力することが求められていたわけです。
この「安保条約の原点」はその後も引き継がれていきます。日本の歴代政権は、安保体制の強化に向けて着々と手を打ってきましたが、その目的はアメリカが始める戦争に日本が協力することです。これまでの準備は、全てその一点を目指して積み重ねられてきました。日本を防衛するためだけであれば、現行憲法に対する政府解釈でも十分対応できるはずです。解釈改憲で対応できないのは、「日本防衛」以外の事態です。集団的自衛権の容認は、日本防衛のためではなくアメリカやアメリカ軍を守るためにこそ必要なのです。
このような集団的自衛権に抵触する安保体制強化に向けての動きは、冷戦体制が崩壊し、他国からの武力侵攻の可能性が低下してからの方が、かえって活発になっています。90年代中葉以降をとっても、95年の物品役務相互提供協定(ACSA)の締結や日米安保共同宣言への署名、97年の改正駐留軍用地特別措置法と新ガイドラインの策定、99年の周辺事態法など新ガイドライン関連法や通信傍受法などの成立、2001年のテロ対策特別措置法と改正PKO協力法の成立などがあります。
そして2002年の今、武力攻撃事態法など有事関連3法案と個人情報保護法などメディア規制3法案が登場しました。これらは「戦争ができる国」への準備だといえるでしょう。しかし、ある日突然、他国から日本が攻撃されるとは誰も予想していません。そのような可能性はほとんどありません。日本だけではなく、先進国が他国から武力攻撃にさらされたことは第2次世界大戦後一度としてありません。
それなのに何故、「武力攻撃事態」法なのでしょうか。それは、米軍が引き起こす戦争に日本が国を挙げて協力する体制を作るためであり、その結果としての「武力攻撃」が想定されているからでしょう。その意味では、米軍による軍事活動への協力という「安保条約の原点」は、そのまま今日における「安保条約の現点」に結びつくものとなっています。豊下報告のネーミングは、まさにこの意味で秀逸であったと思います。
しかも、ここで忘れてはならないのは、第二次世界大戦後、アメリカは多くの戦争やクーデターに関わってきたということです。ベトナム戦争や湾岸戦争、ソマリアへの介入や最近ではベネズエラのクーデターへの関与など、その例には事欠きません。しかも、ブッシュ大統領は「悪の枢軸」論を唱え、イラクや北朝鮮に対する武力攻撃の意図を隠していません。それに、1994年4月には、アメリカは北朝鮮への武力攻撃を準備したことがあり、日本の戦争準備態勢の不備から武力的手段を放棄してカーター元大統領を派遣しての外交交渉に切り替えたという過去があります。もし、この時、周辺事態法や武力攻撃事態法が成立していたら、事態は違っていたかもしれません。
ブッシュ政権は戦争を欲しています。そのための準備は世界各地で進められており、その一つの現れが有事関連3法です。これらの法律は戦争を防止するものではなく、イラクや北朝鮮へのアメリカの介入戦争を誘発する可能性があるということを考えてみるのも無駄ではないでしょう。
歴史は過去のものであると考えるのが一般的です。しかし、現在は過去からの継続ですから、歴史と切断されているわけではありません。歴史になりきれていない過去、過去になりきれていない現在という「灰色の領域」が存在することになります。あえて言えば、現在のあり方を規定する過去-それが同時代史でしょう。安保体制をめぐる「原点」と「現点」もまた、このような関係にあると言えます。
現在のあり方を規定する過去の解明によって、よりよく現在を理解するための一助とする。同時代史学会の存在意義と役割はここにあると考えますが、いかがでしょうか。
新世紀を迎え、独立を達成しての50年目の年に、新たな“知の交歓の場”としての同時代史学会が創立されることは、一介の大学院生として大変心喜ばしいことと思います。
4月27日の立教大学での創立準備大会では、会場に入りきらないほどの聴衆が集い、関心の高さを窺わせました。大会準備の一端をお手伝いさせていただいた私も、当日これほどの方々が来場されるとは考えておりませんでした。用意をしていた椅子に限りがあり、立ち見の方が出てしまったことは、反省しつつも嬉しい出来事でした。
豊下、浅井両先生のご報告は、従来の研究蓄積に対し最新の研究の成果を織り交ぜつつも、創立準備大会に相応しい大局的かつ大胆な内容だったと思います。また、コメンテーターの方々の講評はまさに的確で、やはり大変興味深い内容であったと思います。
こうした華々しい一歩を歩み始めた同時代史学会ですが、将来に向けて若干の課題もあるようにも思います。それは、これまで学界を担ってきた他の学会や研究会との間の連絡についてです。私たち大学院生にとって、報告や発表の“場”が多くなることは大変歓迎すべきことですし、喜ばしいことであります。しかしながら、そうした“場”が、互いに“競合”することは良いことですが、“重複”してしまうことはできれば避けたいものです。そのためにも、ぜひこの点の調整を期待し、よりよい同時代史学会を創っていただきたいと私は望みます。
同時代史学会の設立準備大会(4月)や研究会(7月)に参加し、その正式な発足が楽しみな一方で一つの疑問を感じている。それは、「同時代史」とはいつのことをいうのか、「同時代史」=戦後史・現代史なのか、ということである。「設立趣旨書(案)」をみてみると、確かに「同時代史」=戦後史・占領史というイメージを強く感じなくもない。創立準備大会に参加した知人の多くも、自分の研究対象は戦後ではなく戦前だから、あるいは日米安保や占領史は関係ないから、参加しないかもしれないと述べていた。
しかし個人的には、「同時代史」は、戦後史が主軸となるのは当然のこととしても、戦前と断絶させるのではなく、むしろリンクさせるように、少なくとも昭和期にあたる1930年代くらいまではその範疇と捉えてもよいのではないだろうかと考える。それは、私の主な研究対象が1940年代前半だからなのかもしれないが、いずれにしても、同会において時代的にも分野的にもより一層幅広い参加者が得られるように、戦前も視野に入れて戦前と戦後を関連づけるような企画もしていただけたらと思う。時代的にも分野的にもより一層幅広い参加者が得られることは、同会にとってきっと大きなプラスになるに違いない。
創立準備大会には、多分野からの参加者を願ってのことと思われるが、多分野からの報告・コメントが、連ねられた。このような意欲的なプログラムによってであろうが、多分野から多くの参加者を得られたように見受けられた。
私自身、個々の報告・コメントは、興味深く拝聴させて頂いたが、質疑応答が、個々の報告・コメントに対してのものが多かったことから、バラバラの報告・コメントといった印象を受けてしまったのが残念であった。
このような多分野からの参加者によって構成される学会が、存立していくためには、各分野のバックボーンを有しつつも、その垣根を飛び越えて「同時代」を研究する上での共通認識を構築することへ向けて模索していくことが、必要があるのではないでしょうか? そのための第一歩として、「同時代を研究する意味」といった同時代史学会の存立基盤と言えるものを構築していくことが求められているように思われます。
半世紀前につくられたこの国の憲法が世紀転換期の今、賞味期限が切れたと見るか、芳醇な香りを解き放っていると見るか、ひとえに同時代史のひだにどこまで分け入ることができるかにかかっている。
憲法の場合それは、制憲時の過去を、どこまで現在の目で読み解くことができるかにかかる。「歴史とは現在と過去との生き生きとした対話」(E・H・カー)なのだから。
その時はじめて私たちは、変革過程に関与した同時代人の隠された動きを知ることができる。その動きこそか今、憲法が問い返す新たな意味ではあるまいか。
“密室の七日間”の米国製即席憲法などと自虐できない重い意味につながる。それを土着化と国際化の動きと約言できる。
実際、米国側の制憲の動きに先立って日本側の改革者たちは、体制変革の動きを早くから見せた。ジェンダーから体制のセーフティネット化にまで及んでいる。
まずポツダム宣言のビラを見た後四五年十月、婦人参政権の閣議決定にまで持ち込ませた市川房枝や、堀切善次郎(元東京市長)らの動きが、のち憲法一四条、二四条に組み込まれるジェンダーの視座を浮き上がらせる。
また高野岩三郎や森戸辰男、芦田均ら文化人連盟や憲法研究会に結集したリベラルな言論人の動きが、制憲への土着の動きを浮上させる。
米国総司令部は、四五年十二月に発表された憲法研究会草案を逐一検討し、明治民権期・植木枝盛案を英訳し、制憲工程に組み込んだ。その流れが四六年夏、衆議院憲法改正小委員会で再び強められた。
「貧乏で有為な青年たちが高等教育を受けることができるようにしなくてはならない」「失業者や疾病者が不安にさらされない社会に変えなければならない」――森戸たちは、自由競争の跋扈する資本主義にセーフティネットを張る必要を、小委員会で説きつづけた。それが「健康で文化的な最低限度の生活」を国が保障する二五条の生存権規定の創設や、二六条の教育を受ける権利に受容され、敗戦後祖国の文化国家化の構想につなげられた。
憲法を貫くもうひとつの流れ――国際化のそれを私たちは、憲法前文や九条に求めることもできる。
そこに体現された国際協調主義と平和主義は、議会主義や基本的人権とあいまって、戦後日本の骨格をつくりながら、それに先立って制定された国連憲章に通底していた。人間の安全保障論への視座だ。
両者は共に、戦間期ケロッグ・ブリアン不戦条約に淵源を持ち、戦争違法化の系譜に立つ。九条と憲章二条四項と不戦条約との文言が酷似した現実が、それを象徴する。
憲法制定から六年半後、サンフランシスコ講和がつくられ、五二年四月、日米安保条約と共に発効した。その半世紀目を期して先頃、「同時代史学会」の創立準備大会が開かれた。占領戦後史を基点としつつも一国主義の殻から出てジャーナリストや市民、世界にも開かれた若い学会の創設である(学会入会申し込みは次のメールアドレスまでakimasa@bun.l.chiba-u.ac.jp)。
「サンフランシスコ講和50周年を考える」を共通テーマとしたその日、戦後史の神話が幾重にもあらわにされた。今日に至る全土基地化と北方領土問題をつくり、アジアとの共生を拒んだ吉田ドクトリンと“さわやかで薄っぺらな”戦後民主主義の原型が浮き彫りにされた。
それが冷戦終結後、グローバル化と一極覇権主義の下で地域経済が冷え込み、戦後最大の失業者と自殺者を出しつづける「第二の敗戦」の意味を問い直させている。
しかもその「敗戦」下で世界第三の軍事大国と化し、アジアとの真の共生を拒みつづける。いったい私たちにとって戦後とは何であったのか。
その外交の現在が、戦後改革の原像を忘れて虚構の“有事”に奔走する冷戦後日米関係の陥穽と重なり、今私たちにもうひとつの同時代史を求めつづけている。
学会といえば学者先生の集まり、というのが通り相場だろう。そこで、「お互い先生と呼ぶのをやめることから始めよう」と宣言して動き出したのは、「同時代史学会」設立準備の皆さんだ。
4月27日、東京都内で開いた創立準備大会には、歴史や政治、経済なとの研究者やジャーナリストら約150人が集まった。「サンフランシスコ講和50周年を考える」シンポジウムを催したあとの設立総会で、今秋の正式発足を目指して具体的な活動に移ることを確認しあった。
混沌とした今日の状況は、占領史と戦後史の原点に立ち返って多面的に議論し、とらえ直す必要がある。そもそもこれまでの戦後史自体、日本固有の観点でとらえる一国主義に陥りがちだった。アジアを視座に市民にも開かれた幅広い研究活動が必要だ。
発起人を代表して、進藤栄一筑波大教授は、明治、大正、昭和にわたって在野から「同時代史」を書き続けた三宅雪嶺と、「歴史とは現在と過去の生き生きとした対話だ」という歴史家E・H・カーの言葉を引き合いに、新学会をつくる趣旨をこう話した。
シンポジウムにはジャーナリストも参加、戦後の平和と民主主義、沖縄と北方領土、朝鮮半島の分断などについて、改めて多角的な検討が必要なことを話し合った。
広島、長崎、沖縄などで戦争体験を訴え続けた同時代の語り部たちが次々と逝く。こういう民衆や地方の視点を含む、開かれた研究の場が広がってほしい。〈大和修〉
http://www.korea-np.co.jp/sinboj/sinboj2002/5/0529/52.htm
戦後日本の歴史的研究を共通の基盤とする新たな知の集団を設立するために、4月27日、東京・豊島区の立教大学太刀川記念館で「同時代史学会設立準備大会・準備総会」とシンポジウム「サンフランシスコ講和50周年を考える」が開かれた。
学者、ジャーナリストら153人が参加したシンポジウムでは、筑波大学・進藤栄一教授が発起人を代表してあいさつし、東京大学・伊藤正直教授が総合司会を、一橋大学・森武麿教授と獨協大学・福永文夫教授が司会進行役を務めた。
あいさつで進藤教授は、改めて戦後と民主主義の意味を踏まえながら、今日それを問い直していかなくてはならないと述べ、「歴史とは過去と現在の生き生きとした対話だ」という歴史家E・H・カーの言葉を引用しながら、広く世界に向けて開かれた国際社会の視野の中で、上から見下ろしたものではなく、市民の目で、未来に向けて開かれなければならないと話した。
この日行われたシンポジウムでは、関西学院大学・豊下楢彦教授が「安保条約の原点と現点」について語った。
豊下教授は、サンフランシスコ講和50周年は、同時に日米安保条約50周年の歴史であることについて触れながら、安保条約をめぐる政治・論壇変遷の配置を図入りで解説。さらに現在の朝鮮半島問題、台湾危機問題、昨年9月11日のNY同時多発テロ事件などと関連して、日本の軍事的リアリストへの「移行」が進められていると述べた。
日本は第2次世界大戦後、国連の名の下に米国の占領下に置かれ、サンフランシスコ講和によって平和国家化、非軍事化、民主化することを方針としたが、米ソ冷戦時代の到来とともに、日米安保体制に基づいて、米国のアジア戦略基地としての役割を果たしてきた。
豊下教授は、米国から自立できないままでいる日本の実状について「安保を取っても講和を取っても、外交の不在を指摘せざるを得ない」と話し、冷戦終結後の現点において、吉田ドクトリン・講和条約の最大の欠陥点として「アジア外交の不在」、独自外交機軸の欠落を批判した。
また、豊下教授は、互いの「価値観」論、不戦関係の構築、朝鮮半島および中国問題の解決にも取り組む必要があり、これらが今後の日本アジア外交において大きな批准を占めるであろうと予測した。
シンポジウムではまた、成城大学・浅井良夫教授が「『日米経済協力』構想と経済自立」について報告し、コメンテーターとして、外交・アジア・文化の視点から、立教大学・李鍾元教授、電気通信大学・安田常雄教授らが発言した。
李鍾元教授は、「戦後日本のアジア外交の不在は、50年を経て今日まで継続されてきたものである」と言いながら、その不在、欠落が、戦後日本の積極的、戦略的選択によるものであったこと、また、日本が日米の機軸に沿った経済復興、再生を後押しするために、朝鮮などの「脅威」を利用してきたと指摘した。
また、安田教授は、大衆文化の視点から「サザエさん」「まっぴら君」など戦後の漫画を示しながら1955年以降、大衆文化においても社会性、政治性を含んだ作品が姿を消すようになったと語った。
会場参加者と報告者、コメンテーターの間で質疑応答も行われた。
会場からは「1950年代において(日本と)南北朝鮮との国交正常化の可能性はあったのか」との質問も寄せられたが、これに対し李鍾元教授は、分断国家のそれぞれと国交を結ぶことは、当時非常に困難なことであったと話しながら、しかし当時から日本は朝鮮半島の問題に対して非常に消極的で、アジアとの長期的なシステム作りに対してもその発想自体が欠如していたことを指摘した。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik/2002-04-28/11_0402.html
内外の政治、歴史、憲法の学者らによる同時代史学会の創立準備会が二十七日、東京・立教大学で開かれました。
準備会に先だってシンポジウム「サンフランシスコ講和50周年を考える」が開かれ、百五十人の参加者を前に豊下楢彦関西学院大教授が「安保条約の原点と現点」、浅井良夫成城大学教授が「『日米経済協力』構想と経済自立」と題して報告しました。
豊下氏は、日本はいまアジア外交の構想力が問われているとして、「アメリカを中心とした二国間同盟条約網の枠内での日米韓軍事協力の強化」ではなく、「日中韓提携強化」こそ望ましいと強調。それは日韓関係が「結節軸」だが、歴史認識をただし、不戦関係の構築などが新しい平和・秩序安定には必要だとのべました。
憲法九条、サンフランシスコ講和条約、日米安保条約、吉田茂首相の対米交渉など戦後日本の枠組みを形成した諸問題をどう見直すかをめぐり討論しました。
準備会では発起人の一人、進藤栄一筑波大学教授が名称を同時代史学会としたことについて、「“日本一国主義”に陥らず戦後の歩みを客観化したい」と説明し、市民に開かれた学会をめざすとのべました。
同時代史学会の2002年9月までのあゆみを概観しておく。目的は以下の2点。第1は会員の方々に、とくに運営委員会がどういうことを議論し、決めているのかをお知らせするためであり、第2には、この学会自らの「歴史」を記録しておくためである。いずれはウエッブ上にArchiveを作ることを考えたい。
時期を本学会の創立準備大会・準備総会が開かれた2002年4月27日以前と以後で分けて記載する。とくに初期の記録を正確にするためには、必要に応じて関係者がそれぞれ発言することが望まれる。
本学会設立の発端は、2001年3月末、ある出版企画に関して集められた人びとのうち、いわゆる「戦後史」に関する分野を専門とする者のあいだで、政治史、経済史、文化史、社会史、思想史など狭義の専攻を越えて議論するための学会が必要なのではないかとする話が起きたことにある。
2001年4月27日、東京新宿に数人が集まり、上の話の内容を具体化する会議をもった。はじめはそれぞれの専攻分野の状況を話すところから始まった。また、かつての占領史研究会のありようが話された。「戦後史」に関する学会を発足させるかどうかは、未定のまま、もう一度集まって議論することを決めた。
同年7月6日、東大経済学部で開かれた会議で、各分野の状況の報告と、「戦後史」という呼称の問題性についての議論が行われた。後者は、板垣雄三「<戦後史>批判」(永原慶二・中村政則編『歴史家が語る戦後史と私』吉川弘文館、1996年)が題材であった。このときに、学会の名称として「同時代史学会」という案が出されている。
同年9月21日、東大経済学部で、新たなメンバーを交えての会議が開かれた。学会を発足させるのであれば、さらに輪を広げることが必要であるということが、了承された。この時は、ニューヨークの事件の直後でもあって、具体的な話はそれほど進まなかった。
同年11月2日、東大経済学部で新たなメンバーを交えて会議を開き、2002年度に学会発足を目指すことを決めるいっぽう、政治学関係と経済学関係はメンバーが多いが、それ以外の分野が少ないこと、集まっている人間の平均年齢が高すぎるのではないか、などの問題点と対策が話された。とくに中心となるメンバーを若手で募っていくことなどを申し合わせた。
同年12月7日、明大研究棟で会議を開き、2002年4月28日はサ講和発効から50年なので、その前日に学会の創立(準備)大会を開くことを決めた。当日の企画とともに設立趣意書、会則案を討議し、発起人を募っていくことなどを申し合わせた。この前後から、集まった人間で担当者のグループを決め、必要な案件の原案を討議する方式を採用した。このとき、集まりを会則案との関係で運営委員会(準備会)と称することとした。
なお翌12月8日、運営委員会のメーリングリストを設置した。また12月7日以降の会議は、運営委員会レベルでの討議内容は議事録を作成して、ファイルとして蓄積することとなった。
同年12月28日、東京新宿で創立準備大会関係者会議を開き、企画内容と準備を話し合った。
2002年1月25日、明大研究棟で運営委員会を開き、新たなメンバーを交えて、準備状況、組織体制、趣意書・会則案などを議論した。
以後、同年2月23日、3月22日、4月6日に専修大学(神田)で運営委員会を開き、会の創立に向けて体制を整えた。3月からは4月27日に関する宣伝もはじめ、創立準備大会を迎えることになる。
なおこの間、運営委員会で申し合わせたいくつかのことを記しておく。まず運営委員は全員が実務を含めて会の活動を支えるということである。会員への書類発送作業なども実際に全員が従事している。また運営委員会の連絡はE-メールを基本にし、会議の当日も議題等のコピーは原則として配布しない。これは会務担当や会議担当校委員の負担を減らすためである。また、会の内部では「先生」の呼称は廃止する。これは会員が職業や地位などに関係なく全員対等平等であることをめざそうという趣旨からである。そして運営委員など役員の年齢は65歳以下とする。これは、できるだけ若手が活動の中心になる学会をめざそうとの理由からである。その他、会則(案)にも、上記した点と同種の趣旨がもりこまれている。
4月27日立教大学で、午前中に運営委員会(準備会)、午後に創立準備大会・総会が開催された。準備大会には156人が参加し、『朝日』『毎日』『赤旗』『朝鮮日報』の各紙が、同時代史学会発足ならびに関連する記事を載せた。午前の運営委員会は、準備総会に諮る案件を決め、午後の総会では趣意書・会則(案)それぞれについて修正の意見が出た。これらは12月の創立大会で正式に決定される予定だが、当日フロアから出た意見で、運営委員会で「検討する」こととなったのは、以下の通りである。
これらの意見は、5月以降の運営委員会で諮り、全て案として変更された。ただし、当日でた「・学部学生の会員を考えるべきではないか、また『団体会員』の規定を設けるべきではないか。」という意見に関しては、運営委員会の結論はでていない。
なお創立準備大会では、以下の役員が選出された。いずれも2002年末の創立大会までの任期である。
運営委員(創立大会まで)/浅井良夫(成城大)、天川晃(放送大)、雨宮昭一(茨城大)、池田慎太郎(筑波大)、伊藤正直(東京大)、今泉裕美子(法政大)、遠藤公嗣(明治大)、岡田彰(拓殖大)、加藤洋子(日本大)、黒川みどり(静岡大)、Andrew Gordon(Harvard)、進藤栄一(筑波大)、豊下楢彦(関西学院大)、永江雅和(専修大)、中北浩爾(立教大)、兵頭淳史(専修大)、福永文夫(獨協大)、三宅明正(千葉大)、宮崎章(筑波大附属駒場中高校)、森武麿(一橋大)、安田常雄(電気通信大)、渡辺治(一橋大)
監査 疋田康行(立教大)
運営委員会は、その後5月26日に立教大学、6月21日に専修大学(神田)、7月18日に専修大学、9月9日に立教大学で、それぞれ開催された。
また、7月18日には、専修大学(神田)で、久保谷洋氏を講師に「現代史資料と情報公開制度の問題点」と題する研究会を開催した。出席は40人で、とくに若手の参加者が目立った。
5月から7月にかけて毎回の運営委員会で話されたことは以下の通り。入会者の了承。学会年報の発行準備。創立大会の準備。研究会の企画。会費問題。12月以降の組織。
創立大会の準備について述べると、日程は12月8日、場所は嘉悦学園本部を予定している。また研究会では10月14日に若手研究者の報告会開催を決定した。
なお、とくに6月以降の運営委員会で深刻に議論されている問題に会費納入状況がある。率直に言って芳しくないので、未納の方にはよろしくお願いしたい。
創生期の組織はみなそうであるかもしれないが、同時代史学会は手作りの組織という色彩が濃い。運営委員会ではとくにそのように思われる。手作りの組織を維持し発展させるために必要なのは、活動的で積極的な人びとが多く加わることと、会員に全ての情報が徹底して開示されているなのではなかろうか。
ホームページはまだ開設されていないが、運営委員会のメーリングリストにはすでに膨大な情報が蓄積されてきている。近い将来に会員がいつでもこれらの全ての情報を入手できるような仕組みを作りたいと考える。
第二次世界大戦が終結し、まがりなりにも主権を回復してから50年目の今日、平和への疑念と民主主義への懐疑が広がりをみせている。私たちは、戦後改革の遺産を忘れて時代の方向性を見失い、知の根拠地すら喪失し始めている。いったい「同時代としての歴史」から何を学び、何を継承すべきなのか。もう一度、その原点にまで立ち返り、様々な角度から検討を加え、ともに語り合う意義は決して小さくない。
冷戦後の混沌やむことない21世紀の門出にあたって私たちは、戦後日本の歴史的研究を共通の基盤とする新たな知の集団を、ここに設立する。占領史研究の豊穣な成果を継承し、史資料に基づく実証性に執着しながら、世界史の文脈と比較の視座を重視して、専門分野を横断する総合的な同時代史の創造を目指す。また、国境の壁を越えて海外の研究者と手を携え、狭いアカデミズムの壁を取り払い、世代の壁を克服して、幅広く同時代史の構築に努める。
同時代史学会は、その志において、日本を主たる対象としつつも世界に向けて開かれ、専門性を尊重しつつも市民に向けて開かれ、過去を見据えつつも未来に向けて開かれていなければならない。むろん、それは容易なことではない。しかし、そうした絶え間ない試みのなかから、私たちは初めて、同時代史をともに学ぶ“知の交歓の場”を創出することができるであろう。
(付則)
*会費は年あたり、一般の方5,000円、院生の方3,000円を予定しています。
**団体会員を設けるかどうかは、今後引き続き検討します。
| 日時: | 10月14日(月・祝日) 13時30分~17時 | |
|---|---|---|
| 場所: | 立教大学 12号館第1・2会議室(地下1階) | |
| 共通テーマ: | 1960年代の政治と経済 | |
| 報告1 | 菊池信輝氏(一橋大学大学院) | |
| 「1960年代の財界と政治」 | 40分 | |
| コメント | 武田晴人氏(東京大学) | 10分 |
| 討論 | 30分 | |
| 報告2 | 岡田一郎氏(筑波大学大学院) | |
| 「日本社会党の組織問題 - 1960年代を中心に -」 | 40分 | |
| コメント | 空井護氏(東北大学) | 10分 |
| 討論 | 30分 |
去る4月27日の設立準備大会において、2002年度の予算が承認されました(数値は別表参照のこと)。会計年度は4月から3月までとし、一般会員の会費年額5,000円、院生会員の会費年額3,000円が決まりました。
また2002年度(2002.4~2003.3)は、会誌を発行しませんが、会費はこの額とし、それを集めて会誌の基金とすることが了承されました。
何分にも設立間もない会ですので、経済基盤が弱体です。会員の各位にはスムーズな会費納入にご協力お願いします。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| (収入) | ||
| 会費収入 | 650,000 | (一般100名、院生50名) |
| 収入計 | 650,000 | |
| (支出) | ||
| ニューズ・レター編集費 | 100,000 | (2回発行) |
| 通信費 | 54,000 | |
| 大会費用 | 50,000 | |
| アルバイト料 | 90,000 | |
| 年報発行準備費 | 100,000 | |
| 支出計 | 394,000 | |
| 来期繰越金 | 256,000 |
同時代史学会の第1回の研究会を、さっそく7月に開くことができました。朝日新聞社で情報公開問題にずっと取り組んできた久保谷洋さんに報告をお願いできました。当日のレジメを再録します。研究会の様子は森茂樹さんの参加記をご覧ください。
情報公開法について 2002年7月18日 久保谷 洋 1 情報公開の現状 1.1 地方レベル 82年4月山形県金山町 2001年4月1日現在、普及率66%(前年42%) 1.2 国レベル 80年10月、文書閲覧窓口制度 93年8月細川首相が前向き発言 94年9月自社さ3党合意(2年以内に法案の内容をまとめる) 94年12月行政改革委員会が発足、行政情報公開部会で検討 96年12月橋本首相に「最終報告」を意見具申 99年4月に成立 2001年4月1日施行 2001年11月独立行政法人対象の情報公開法成立→2年以内に施行 2 情報公開法案の特徴 2.1 一般的な特徴 2.1.1 アカウンタビリティー<1> 国民主権の理念 「政府の諸活動を国民に説明する責務」 2.1.2 開示請求権の明記、原則公開の基本的枠組み<3、5> 行政文書が原則として公開であるという「基本的枠組み」 2.1.3 不開示情報→定性的方式、侵害のテスト<5> 2.1.4 独立した第三者的な不服審査会(情報公開審査会)の設置<21以下> インカメラ審理<27I>、ボーン・インデックス<27III> 2.2 自治体条例との比較 2.2.1 請求権者……「何人」<3> 2.2.2 対象機関……国の行政機関すべて<2> 2.2.3 対象文書…‥「組織共用文書」、電子情報<2II> 3 情報公開法の問題点 3.1 中心的な争点 3.1.1 ?知る権利の明記 3.1.2 不開示情報 △公務員の氏名 ?公開特約情報 ▲防衛・外交・捜査情報→行政機関の長の一次的判断権尊重 3.1.3 ▲存否応答拒否処分(グロマー拒否)<8> 3.1.4 ▲手数料<16> 3.1.5 その他 ×適用除外機関の問題 ×刑事記録 3.2 残された課題 3.2.1 議会・裁判所 3.2.2 地方自治体 4 情報公開法の活用 A社では法律施行と同時に約900件(うち東京本社分が約500件)を一斉請求した。 開示・不開示の内訳(東京分のみ集計)は、以下の通り。 全面開示 15% 全面開示と部分開示Aを合わせると、約 部分開示A 17% 3分の1となり、かなりの開示率。 部分開示B 6% *部分開示Aは「内容に至るまでかなり 全面不開示 20% の部分が開示されたケース」。部分開示Bは 不存在 32% 「開示とは名ばかりで、全面不開示に近い 取り下げ・その他 10% ケース」をいう。 なお内閣府の情報公開審査会での逆転率は42%(全面認容6%、一部認容36%)。 5 歴史研究と情報公開制度 5.1 対象となる文書 およそ、近代国家になって以降の全文書 5.2 問題点 5.2.1 個人情報 5.2.2 不存在 5.2.3 著作権 5.2.4 「歴史的・文化的資料」 5.2.5 各刑事記録
表記研究会は2002年7月18日(木)18時より、専修大学神田校舎203教室において、報告者に久保谷洋氏をお迎えして行なわれた。
周知の如く、昨2001年4月より情報公開法が施行され、政府・地方公共団体の保有する行政文書の閲覧が可能となった。本制度の趣旨が国民主権の理念にのっとって行政機関の「説明責任」を明らかにすることにあるのはもちろんであるが、資料発掘に多大な精力と時間を費やさねばならない現代史研究者にとってもたいへんに喜ばしいことであり、実際、この制度を利用して、戦後外交に関する新資料や「大正天皇実録」等が公開の運びとなったことはいまだ記憶に新しい。
しかしながら、情報公開制度はかなり複雑なもので、開示請求の手続きに相当の手間を要するのみならず、重要な情報のいくつかが公開の対象から抜け落ちる欠陥も指摘されている。かかる制度を十分に生かすためには、その特徴や問題点を知悉し、行政機関に対抗し得る「武器」として使いこなすすべを心得ておくことが必要であろう。
報告者の久保谷氏は朝日新聞社において本制度を利用した資料発掘のプロジェクトに従事され、条文や運用の細部までに精通している。体調の不振をおしての報告だったにもかかわらず、長時間にわたって熱弁を振るわれ、フロアからの質問にも丁寧すぎるほどのお答えいをいただくことが出来た。以下、レジュメを捕捉する形でその内容の一端を紹介してみたい。
この情報公開法は、一般的原則という点から見ればよく出来ている。対象となる文書には決裁済み文書のみならず「組織共用文書」や電子情報を含めることで内部資料の閲覧も可能とした。また、不開示の範囲が不当に拡大しないように、事項的方式(特定の項目に該当する場合に不開示となる)ではなく、定性的方式(開示のリスクが一定限度以上の場合に不開示)としたこと、独立した第三者機関による不服審査制度を設け、この機関にインカメラ審理(不開示文書の実地検分)の権限を与えたこと、部分開示で墨塗りとなった箇所にはその根拠となった条文を提示することを義務付けたことなどは、行政機関による恣意的な運用を防ぐ上で意義のあることである。
しかしながら、本法には十分な情報公開を妨げる欠陥も多々認められる。たとえば、外交・安全保障や捜査情報の開示の可否決定については、当該行政機関の長の判断が尊重されることとなっており、「国家機密」の恣意的な拡大の恐れなしとし得ない。また、個人情報は非公開とされるが、この結果、たとえば天皇のような歴史的な重要人物に関する情報の公開が妨げられる恐れもある。
より問題なのは複雑な開示手続きを悪用した妨害が可能であることである。たとえば病歴や逮捕歴などは、記録の存否それ自体が重要な情報になる。ゆえに、「存否応答拒否」(あるかないかも答えない)という処分が認められているが、これを濫用された場合、請求者側の不服申し立ては極めて困難となる。また、請求手数料は「一件」300円と定められているが、膨大な文書群が開示されるとき、それを何件と数えるかによって手数料はかなり違ってくる。実際には件数はかなり細分化して数えられており、莫大な手数料を請求される例も珍しくないという。こうした欠陥ゆえに多くの請求が「門前払い」を受けるとすれば由々しきことであろう。
また、現代史研究にとって最も重要な歴史的・文化的な資料は、別に公開の制度を定めるとして、情報公開法の対象とする「行政文書」からはずされている。この結果、防衛研究所や外交史料館で保管される文書が非公開となってしまう恐れもあるのである。報告者は一例として、防衛研究所が所蔵する文書の目録を示された。この目録自体は「行政文書」として本法の適用対象であるが、日記・日誌類の一部が個人情報にかかわるとして黒く塗り潰されている。目録が明らかでないのだから、この目録に対応する実際の文書類(こちらは適用対象外)が非公開であっても、その理由は判然としないし、不服申し立ても難しい。それどころか、重要な資料が存在を知られないまま眠っていることもありうるのである。
防衛研究所もここ数年ほどで随分公開が進み、門外不出であった「嶋田繁太郎日記」の公開や「機密戦争日誌」の活字化・刊行などの瞠目すべき成果もある。しかし、依然として多くの非公開記録が残っていることも事実である。また、外務省所管の日米関係にかかわる文書のなかには、米国側で公開されているにもかかわらず頑なに公開を拒まれているものがあることはよく知られている。
行政機関の側にしてみれば、開示した情報を元に何かの責任を追求されてはたまらない、という感情があるのであろう。特に戦後補償問題などに神経質になることは想像に難くない。しかし、行政文書は行政機関の私物ではなく国民の共有財産であり、情報公開はお上の恩恵ではなく、国民主権原理の当然の帰結である。この制度がより多くの人々に利用されながら内実を整え、欠陥を克服してゆくことを願ってやまない。
12月8日に、同時代史学会は創立大会を開きますが、その企画は、大きく二つの柱で開催する予定です。
第1の柱は、「同時代史の中の戦争」と題する大型シンポジウムを行います。本シンポジウムでは、現在、その枠組みが大きく変動しつつある第二次世界大戦後の世界と日本の歩みを、アジア・太平洋戦争から現代の戦争に至る、戦争に焦点をあててふり返ろうというものです。
アジア・太平洋戦争が戦後日本の出発点を規定したことをはじめ、朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争と続く戦争は、戦後日本の進路の決定と転換に大きなインパクトを与えました。それのみならず、戦後史の重要な岐路には、必ずといってよいほど、この戦争の評価や見直しが繰り返し行われてきました。このように、戦争とそれについての評価の変遷という視点から戦後の歴史をふり返ろうというのが、シンポジウムのおおまかな問題意識です。
報告は、アメリカ、アジア、日本のそれぞれの視点から、戦争に焦点をあてて、同時代史をふり返る報告をお願いし、そのうえで3名のコメンテーターから各報告につき、自由な立場からコメントをいただき、その後シンポジウムを行う予定です。報告者並びにコメンテーターには、様々な学問分野にわたる幅広い立場の方にお引き受けいただき、同時代史学会の創立大会のシンポジウムにふさわしい活発な議論が行われるのではないかと期待しております。
第2の柱は、「澤地久枝と同時代史を語る」と題して、澤地久枝さんの講演を中心に、コーディネーターとパネリストを交え、戦争、女性、沖縄などの視点から、戦後史を縦横にふり返っていただきます。
当日のプログラムの概要は、以下のようになっています。
なお、場所は嘉悦学園(嘉悦女子中・高等学校:千代田区富士見2-15-1)です。
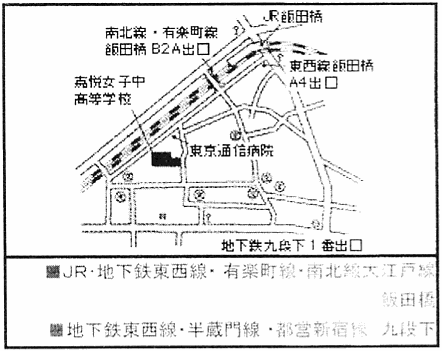
同時代史学会News Letter・創刊号をお届けします(年2回、刊行予定)。
創立準備大会で報告されたように、本学会は「年報」の発行を想定し、その準備も着々と進んでいるのですが、その刊行は早くとも来年以降になります。その意味でこの創刊号は、一部「年報」の役割を加味した構成をとり、創立準備大会関係の記録をはば広く収録することになりました。
第二にこの学会生誕のプロセスの記録として運営委員会報告・収支状況報告をおき、あわせて何人かの方にこの学会への「期待と要望」を執筆していただきました。この「期待と要望」は今後も継続的に掲載するつもりですので、ぜひ自由な提言をお願いしたいと思っています。
そして第三は今年12月の創立大会のご案内を軸に、年数回開催する予定の研究会の報告(第一回研究会の参加記など)、案内情報などを掲載しました。<市民に開かれた同時代史学会>がどのような実質を創り出していけるかは、もちろん今後の課題ですが、このNews Letterがそのための創意とアイディアを発想する機動力にあふれた場として機能することを願っています。(安田 常雄)
まだ十分にNews Letterの編集委員会も機能しているとはいえず、時間との闘いの中でなんとか編集・印刷にこぎつけました。不十分な点があれば、どんどんご意見をお寄せください。第2号で修正していきたいと思います。パソコンのパワーユーザーの方がいらっしゃれば、是非運営委員に入っていただきたいな、と思いながら作業を進めました。「同時代史」を標榜する以上、そうした「技術」も要素の一つかと…。
発送作業は運営委員全員で行います。若い人にそうした作業を任せることはしないという姿勢とも言えます。まず足元の民主化から。(宮崎 章)
| 同時代史学会 News Letter |
|---|
| 発行日 2002年9月30日 |
| 同時代史学会 |
| 連絡先:〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町1-33 |
| 千葉大学文学部 三宅明正研究室 気付 |
| Tel 043-290-3638 akimasa@bun.l.chiba-u.ac.jp |