第3号 (2003年10月) ISSN 1347-7587
第3号 (2003年10月) ISSN 1347-7587
折にふれキャロル・グラック(コロンビア大学教授)の次の発言を思い出す。朝日新聞の「米から見た日本国憲法―歩みと現状・近現代史学者に聞く」という特集(2000年4月29日)の次の一節である。
「戦後」は、ほとんどの国で50年代で終わっている。いまだに「戦後」だと考えているのは日本ぐらいだ。95年に各国が第二世界大戦終結50周年の記念行事をしたとき、日本だけが「戦後50年」だった。
これは、日本国憲法施行55年を前に、日米関係の産物である憲法の歩みを、米側がどう見ているのかを、問うたものである。つづけて彼女は、日本人にとって戦後は、「平和や経済からなる現状の体制を意味」し、日本国憲法がこの「戦後」と結びついているとした。
いずれにせよ、なぜ日本だけが「戦後50年」なのか。1945年が昭和期の切れ目であったことは疑いえない。ここに文字通りの戦後が始まった。他方「55年体制」が生まれ、『経済白書』が「もはや戦後ではない」と言ったのは翌56年のことであった。にもかかわらず、私たちは今生きている時代をなお「戦後」として意識している。なぜ日本だけが「戦後50年」なのか。
ときに蛇行しときに氾濫をよぶこともあった、余りに長い「戦後」史の流れをどうとらえ、それがどのような軌跡を描き、現在という大海に流れ込んだのだろうか、と考えざるをえない。戦後史の水脈は、大海の中でどのような潮を形づくったのだろうか。
本年度大会テーマは、「デモクラシーの同時代史」である。一つは、地域からの民主化をミクロかつ精緻に問うものであり、もう一つは「戦後」日本のデモクラシーをマクロな視点から再検討しようというものである。私そして私たちにとって、「戦後」とは一体何であり、何であったのか、もう一度考えるよき機会としたい。
この学会の「海外会員」には二つのタイプがあると思う。ひとつは海外を主な活動の場とし、多くの場合母語も日本語ではない人々である。もうひとつは、日本を主な活動の場とし、母語も日本語で、何らかの目的で長期間海外にいる人々である。後者の目的は、調査・研究か教育に限られるのではないだろうか。
後者のタイプの海外会員に対し読者が求める情報は、1 滞在先における研究者たちの議論の特徴、2 史資料に関する情報 3 授業の状況(というより、何をテキストにしているかが、外国で教壇に立つ者の間では、重要な情報になっているように思う)、4 その場所に滞在した結果初めてわかった興味深いこと、などだろう。
いま私は、文部科学省の長期在外研究員としてアメリカ、ニューヨーク州イサカのコーネル大学に来ている。東アジア研究のセンター(正式名称はプログラム)と歴史学部に、授業の義務のないフェローとして籍を置いている。コーネルの日本研究の教員たちに関する情報は、ホームページにあるもの以上にはよくは知らない。要するに上の1と3については、ここで述べるところがない。
ただ少し付け加えるとすると、まず東アジア研究のセンターには、韓国からの学者が多く来ていることに驚いた。韓国・朝鮮を対象とした研究者だけでなく、日本を対象とした研究者も複数滞在している。側聞するところでは、韓国の大学ではサバティカルが徹底しており、若手はもとより中高年の研究者もこれを利用して外国で研究に携わる人が増えているそうである。その際、人文・社会系の分野でも、アメリカへ行く人が少なくない。初めは日本へ留学しても、サバティカルではアメリカへ、という人々が多いと聞いた。
もう一つは、コーネルの組織では、教員が属する歴史学や人類学、アジア学など複数の学部の枠を超えて東アジア研究のセンターがある訳だが、そのことの積極面である。他大学のように日本や中国のセンターではなく、「東アジア」となっているのには、もちろん相対的に規模が小さいという理由があろう。しかし毎週一回行われている会議の場で、日本、韓国・北朝鮮、中国・台湾を東アジアとしてくくり、相互に関連させながらさまざまな営みや催しが進められているのをみると、これはむしろコーネルにおける研究体制の「強み」になっているのでは、と思うようになった。この点は別の機会に改めて考えてみたい。
次に2の史資料に関してである。ただしコーネルには大きなアーカイブがない。従ってここでも述べることはあまりない。もちろん図書館の中には、アジア関係の専門図書館がある。蔵書量も少なくはない。もっともそこでは、東アジア、東南アジア等の各地域の言語で書かれた書籍が、同一の基準で分類され、配列されている。率直に言って私には非常に使いにくい。スタンフォード(フーバー研究所)だと、日本語の書籍はそれでまとまって配列されており、バークレーもそうなっていたように思う。
故・前田愛氏の蔵書がコーネルに一括して収蔵されたことは有名だが、日本のように何々文庫(たとえば「向坂文庫」とか「大塚文庫」など)となっている訳ではないので、それも日本に関する書籍のところにばらばらに配列されている。各図書館には独自の歴史と考え方があろうが、これだと「前田愛研究」をする人には不便なのではないだろうか。
なお、今回私は、生まれたばかりの双子の子どもたちを伴ってこちらに来たため、「移動の自由」が事実上なく、各地のアーカイブや声をかけてくれた他の大学を訪れることができない。このままではこの雑文を読んで下さった方に何の情報も提供できない。それでは申し訳ないので、八年前に訪問したバチカンのアーカイブ(アルキビオ)の話を記そうと思う。とくにいま大学院に入ったばかりくらいの方々が役立ててくれるとありがたい。
バチカンには全体のものと各教団単位のアルキビオとがある。日本関係ではイエズス会のもの(プロパガンダ・フィーデ、布教文書館と訳す)などが、大部の史料をもっており、近現代では植民地期朝鮮に関する報告書なども結構なボリュームである。バチカンには、法王の死去があると、三代前の法王の時代のものが公表される原則がある。いま見ることができるのは一九二〇年代はじめまでのものである。
この原則からわかるように、おそらくは近々に、一九三〇年代半ばすぎまでの文書が公表されることになる。いうまでもなくナチズムとの関係がそこに含まれる。ここ数年のバチカンの謝罪ラッシュは、それと関係しているのではないか、と私は思っている。それはともかく、日本に関係する史料のなかにも興味深いものがでてくるのではないか。日本や中国からの報告書には、時代から考えて重要なものがあるはずである。また、これはアルキビオではなく、グレゴリアナ大学の図書館で見たものだが、一九三八年から三九年に、日中戦争に関し、日本の外務省(外郭団体)が、バチカンを通してその主張を欧州に広めようとした資料群がある。これなどほとんど手の着いていないテーマなのではなかろうか。
バチカンのアルキビオは、同時代史にとっても史料の宝庫に見える。ただしその史料は、もちろん英語ではない。教団によってはスペイン語やポルトガル語、フランス語である。英語で可能なのは、ごく一部のアルキビオで、どういう史料を見たいのかの交渉までである。私はイタリア語に堪能な方の同行を得て、ここを訪問することができた。なお訪問時には、調査目的を記した訪問者の所属機関の長の文書が必要である。日本大使館の文書は不要。
8年間を過ごした筑波大学を離れ、2003年4月より、広島市立大学国際学部で、日本政治外交史の講義とゼミを担当させていただいております。遅ればせながら、この場をお借りして、同時代史学会会員の皆様に、着任のご挨拶を申し上げます。
広島市立大学は、1994年開学の新しい大学で、国際学部、情報科学部、芸術学部の3学部・大学院と、広島平和研究所からなっています。原爆ドームのある都心部からバスで15分。長いトンネルを抜けると、緑なす豊かな自然に囲まれた美しいキャンパスが姿を現します。私の勤務する国際学部は、1学年100人定員に対して教員が53人もいる徹底した少人数主義を誇りとしています。国際学部は、国際文化系列、国際政治系列、国際経済系列の3系列に分かれており、学生は2年次からそのいずれかの系列に属し、3年次から履修する専門演習ではほとんどマンツーマンに近い指導を受けることになります。
さて、広島市民となって初めて迎えた8月6日、平和記念式典に参列しました。平和記念公園に向かうため始発電車に乗りましたが、車内は式典に参列する人々が多く、この日が広島にとって特別な一日の始まりであることを実感しました。
冷夏となった2003年ですが、不思議と8月6日は例年通り朝から酷暑となり、参列者は58年前の8時15分に炸裂した灼熱地獄に思いをいたすこととなりました。秋葉忠利・広島市長は「平和宣言」のなかで、「力の論理」ではなく「法の支配」の必要性と、被爆者がその体験から到達した「和解」の精神の重要性を訴え、核兵器を「作らせず、持たせず、使わせない」を内容とする「新・非核三原則」を新たな国是とすべきことを提言しました。日本政府のイラク戦争支持を痛烈に批判した秋葉市長に対し、小泉純一郎首相は通り一遍の演説をボソボソと読み上げ、わずか1時間の広島滞在を切り上げて足早に去っていったのが印象的でした。
平和記念式典への参列者が4万人にとどまったのは1981年以来のことであり、被爆者の高齢化と記憶の風化は年々進行しています。昨年の平和記念式典の「平和宣言」で、秋葉市長は、アメリカ人記者ジョン・ハーシーが被爆者の生の声を初めてアメリカに伝えたルポ『ヒロシマ』が読み継がれなくなっていることに懸念を表明しました。それを受けて今年、本学会の発起人でもある明田川融氏の新訳により、『ヒロシマ 増補版』(法政大学出版局)が刊行されたことは、同時代史学会としても喜ばしい限りです。
実は、8・6の前日まで、私は沖縄に滞在しておりました。元来、講和後の日本政治外交史を研究していた私が、沖縄に関係するようになったのは、かつて沖縄開発庁(現・内閣府)が取り組んだ「沖縄戦関係資料閲覧室」(東京・西麻布)の設立を手伝ったことがきっかけでした。この時の有識者会議メンバーが中心となって始まった沖縄戦と米国の沖縄占領に関する科研費の共同研究に連なることとなり、研究対象として沖縄が加わったのです。
慰霊の日直前まで滞在した6月に続く今年2回目の沖縄訪問では、戦後沖縄にあって、アメリカによる沖縄の信託統治と、沖縄の政治、経済、社会、宗教のあらゆる点にわたるトータルなアメリカニゼーションの必要性を唱え、本土復帰論への収斂とともに歴史の闇へと消えていった特異な政党、「社会党」とその中心的存在であった大宜味朝徳に関する拙い報告を行いました。
かつて羽田空港から訪れた時と比べて、広島-那覇間の飛行時間は約1時間半とかなり短く、広島と沖縄の近さを実感しました。いわゆる「沖縄病」にかかってしまった者のひとりとしては、沖縄が近くなったことは広島赴任の利点のひとつといえるかもしれません。
しかしながら、いまなお戦争と平和の問題を提起し続けている広島と沖縄は、意外にもその平和主義はあまり噛み合っていないのではないか、と思い始めています。いみじくも、沖縄のある若者は、次のように語っています。「広島の若者は核兵器などの知識は豊富なんだけど、すぐに世界平和とかに話を広げる。平和って、もっと身近な問題から考えるべきじゃないかな」(『中国新聞』2003年7月22日付)。
すなわち、広島の平和主義は、原爆投下という世界史的経験に立脚し、核兵器の全廃を求める点でグローバルで普遍的な平和を構想するのに対し、地上戦を経験し、講和後も長らくアメリカの施政下に置かれ、現在もなお基地問題に苦しめられている沖縄は、より身近な問題として平和を求めている、ということができるかもしれません。
この点について、藤原帰一氏は、次のように興味深い指摘を行っています。「現在の戦争記述では、広島よりも、沖縄戦について語られることが多くなった。原爆投下の可能性よりも、沖縄の米軍基地に、過去と現在を結びつけるものが見出されるようになったのだろう」(『戦争を記憶する』講談社現代新書、2001年、133頁)。
本務校で今年度後期に開講する「日本研究」という講義で、私は、戦後沖縄の軌跡をたどりながら、沖縄が<日本>に対して提起する問題を広島の学生とともに考えてみたい、と思っております。沖縄の視座から戦後史や日米安保を語ることは、広島という特別な土地にあっては、あるいは広島の平和主義を「相対化」するものと受け止められ、それゆえ一種の「挑発」と映るかもしれません。しかし、気負っていえば、広島で沖縄を問い続けることは、すれ違いがちな「6・23」と「8・6」の間の距離を埋め、両者をつないでいく作業にほかなりません。「戦争」どころか「戦後」すら知らない世代に属する私ですが、広島に赴任し、沖縄を研究することとなった巡り合わせを、単に偶然以上の何かとして引き受けていこうと思っています。
このたび、2002年度第3回研究会で報告したのは、小倉充夫・加納弘勝編『東アジアと日本社会』(『国際社会』第6巻、東京大学出版会、2002年)に寄せた、同タイトルの拙稿の内容です。その詳細については、関心のある方はこの論文をご覧ください(当日もレジュメはごく簡単にとどめ、論文自体を紹介しました)。本稿では、この『国際社会』と本論文との関係を中心に、報告内容を簡単に述べることにしたいと思います。
昨年刊行された『国際社会』全7巻は、上述2名の編者と、宮島喬、梶田孝道の4名によって編まれたものです。同出版会から1989年に刊行された『講座国際政治』全5巻を意識しての企画で、今回は主として国際社会学、社会学という立場から、多岐にわたる「国際社会」現象を読み解くことをめざした論集ということでした。その構想を聞く過程では、分析方法として、歴史学的でも政治学的でもないアプローチの意義が強調される場面もありましたが、私としては、現代史を基礎とした国際関係学の立場から、今回は他分野への関わりだという意識を若干抱きつつ、参加することになりました。というのは、日ごろ社会学系統の在日朝鮮人研究の成果に学ぶなかで、それらに触発されながらも相違を感じていた諸点 -在日朝鮮人の現状や実態を重視するあまり、見えにくくなりがちな問題の構造性、歴史的背景や東アジアにおける位相等について、若干の問題提起をしてみたいと思ったからです。それは言いかえれば、論文冒頭で述べたように、「日本のマイノリティ」「エスニシティ」として捉えるところから始まる在日朝鮮人研究ではなく、東アジア、ひいては、19世紀末以降の国際関係の展開のなかに在日朝鮮人を捉え、在日朝鮮人と朝鮮半島との紐帯、あるいは「ネイション」としての在日朝鮮人のありかたの変遷を意識してこそ、日本社会における在日朝鮮人の現状についても、より認識を深められるのではないかという視点です。なお、論文構成は以下の通りで、内容の原型は1993年の日本移民学会大会・96年の日本植民地研究会定例会での報告内容、および、96年の大学院博士課程終了論文です。
本論文は、日本が帝国主義体制の一翼を担い、朝鮮を植民地統治する過程で、朝鮮人の居住地が朝鮮半島を大きくこえて強制的に拡散され、そのなかで形成されていった朝鮮人の、いわば「国境をまたぐ生活圏」(梶村秀樹)を前提に、第二次大戦後、冷戦の展開のなかで、在日朝鮮人のこうした「生活圏」が、在日朝鮮人の意に反して遮断されたという観点から、叙述したものです。東アジア冷戦下における日本の講和条約締結、朝鮮分断の固定化のなかで、故郷を包含しての統一「祖国」に期待する在日朝鮮人の意志とはうらはらに、分断状況をそのままに「祖国」との連結がはかられていくこと、在日朝鮮人の朝鮮統一をめざす動きと日本における民族差別撤廃を求める動きとは、本質的には相補的なものとして捉えられること、そして、在日朝鮮人のあいだでも「生活圏」が遮断されたということが実感されにくくなるなかで、「日本のマイノリティ」「エスニシティ」としてのアイデンティティを表明する人も現れてきたこと、とはいえ、南北間の緊張緩和をうけて、在日朝鮮人と朝鮮半島との紐帯は薄れつつあるばかりではないこと、などを論じました。
論文執筆時は石原都知事の「三国人」発言問題や、在日外国人の地方参政権問題・日本国籍取得要件緩和問題などが焦点化されていた時期で、そうした状況を意識しながら記述したのですが、今回、報告するにあたっては、とりわけ昨年9月以来の、北朝鮮との関係が普段にもましてクローズ・アップされている現在における、在日朝鮮人をめぐる状況についてあらためて考える機会にもなりました。90年代以降、特にここ数年の動きとして、ようやく韓国人と朝鮮学校や学校出身者との交流が始まり、韓国の一部では、これを非常に意義あることとして認識されるようになってきたのですが、逆に日本では最近、韓国籍者を含めての在日朝鮮人全般への圧力が、異常なまでも高まっています。この間にみられた、日本人の朝鮮人学校・生徒に対する嫌がらせの数々を想起しても、本論文最後に述べたように、日本の朝鮮植民地統治、東アジアにおける冷戦の展開自体を問いなおす視点が伴わなければ、結局のところ、日本人と在日朝鮮人の共生などありえず、ひいては日本と朝鮮半島との揺るぎないパートナーシップなど築きえないのではないか、と考えます。
昨年末の同時代史学会第一回大会や、国際政治学会大会での部会報告などでも、アジアにおける地域協力、「東アジア共同体」といった構想が提唱されていますが、アジアにおける地域協力、信頼醸成を阻害している重要なひとつが、まさに相互で著しく異なる歴史認識だと思われます。なかでも在日朝鮮人の体験に関しては、認識の共有が遅れている顕著な事例のひとつであり、在日朝鮮人の歴史的足跡をたどりながら見えてくる、東アジアにおけるこれまでの国際関係の実態に学ぶことは、今後の地域協力を考えるうえでも、きわめて重要だと考えます。
ところで、本論文でも引用しました、ブルース・カミングス(Bruce Cumings)の Korea's Place in the Sun : A Modern History (1997) の翻訳がようやく完成しつつあります。明石書店より『現代朝鮮の歴史 -世界のなかの朝鮮』というタイトルで近刊の予定で、私も一部担当しました。この本はもともとは大学のテキストとしての企画で、朝鮮の建国神話から、北朝鮮の核問題や2000年の南北首脳会談に至る(初版に加筆された内容です)時期までの朝鮮の歴史について、米国との関係を重視しながら、カミングスが初学者向けに語ったものです。一国史としての朝鮮史という枠組みをこえて、東アジア国際関係史、ひいては20世紀の世界を、非ヨーロッパの一地域から問いなおす内容となっています。そこに生き、生活している人々の姿を実感しながら、読みすすめられる近現代国際関係史という点で、同時代史について学ぶ私たちにとっても示唆的な本だといえます。関心のある方は、ぜひご一読ください。
*本稿では、朝鮮、朝鮮人という用語を南北総称の概念として使いました。
日本(本土)占領期の沖縄関係の史料を読んでいると、本土の沖縄人(うちなんちゅ)を(自他を問わず)「在日」と呼んでいた例が散見される。現在、「在日」といえば一般的には在日朝鮮人の人々が想起され、沖縄人による「在日」という名乗りの痕跡に関心が及ぶ機会はまずない。占領期から現在までのこの変化には、どのような歴史的経緯、なかんずく沖縄人と朝鮮人の関係の変遷がはらまれているのだろうか。私の報告は、この素朴な疑問に答えるための試論にすぎない。しかし、〈戦後=帝国後〉日本における被差別民衆史の研究が、おおむね各集団の日本社会・国家との関係に終始し、事例の並列にとどまっている現状を越えるためには、必要な習作と考える。
またこの課題は、沖縄史にとっても重要である。「在日」という在り方に着目するならば、沖縄人は単数形で語り得る集団ではない。少なくとも方法的には、在郷土沖縄人と在本土沖縄人を一旦峻別し、あらためて両者のかかわりを検討する手続きが要る。「戦後日本と沖縄」という設定がなされる場合、往々にして在本土沖縄人の歩みは在郷土の人々の流れに還元されてしまい、彼らが在郷土沖縄人と、さらには在日朝鮮人とどのような関係のなかで生きたかという関心は生まれにくい。戦後日本史に沖縄史を補遺として付加するのではなく、沖縄への視点が戦後日本史を内部から変容させる可能性をもつとすれば、その鍵のひとつは、複数の沖縄人を見出す作業のうちに在る。こうした観点は、さらに沖縄の「戦後」が〈戦場後〉かつ〈占領下〉という二重性を持つことを、私たちに痛感させる。この二重の経験は、沖縄人といえど全員が体験したのではなく、その内実も多様であった。在本土沖縄人と在郷土沖縄人のあいだの緊張関係は、この沖縄の「戦後」の二重性に、誰がいつどのようにかかわったかを抜きにしては考えられない。報告では、以上の関心から近代以来の沖縄人による朝鮮人への関心とかかわりを概略的にたどり直すことを主眼とした。
もっとも、現在確認できる限り、ふたつの「在日」社会は人的・組織的に密接な関係を持っていたとはいえない。それどころか、沖縄人にとっては近代以来、いかに朝鮮などの植民地との類縁性をうち消すかが大きな関心事であった。それは関東大震災のなかで、比嘉春潮が自警団に「朝鮮人だろう」と間違えられた際、全力で「ちがう」と否定しなければならなかったところによく現れている。この極限状況での否定は、植民地(とその出身者)に対してふるわれる暴力から身を守るために、ある場合には自分たちが暴力を行使する側に立つ可能性をも暗示する。たとえば本土在住の沖縄学の泰斗、東恩納寛惇は、いわゆる方言論争(1940~41年)において官僚の方言撲滅政策を批判しているが、彼が憤慨するのは、沖縄が朝鮮や台湾と同様、同化の進んでいない社会と見なされる危険を感じたからだった。そこには「ちがう」という必死の否定とともに、真正な帝国臣民として植民地を指導する側に立つ自負が浮かび上がる。
こうした断絶を越えて両者が接近するのは、占領下の日本本土においてである。1945年11月に結成された沖縄人連盟自体、その名称に在日本朝鮮人連盟の影響が認められ、事例はわずかながらも両者の接触が存在した。また本土在住の沖縄人が発行した紙誌では、50年代初頭まで自分たちを「在日」として呼称する事例が確認できる。当時は、自分たちを「非日本人」と認識し、米軍のもとで沖縄が「高度な自治」を獲得する将来を夢見た沖縄人もいた。朝鮮半島・沖縄とも、信託統治下におかれるのではないかと予想される条件下で、国家から投げ出され、それゆえに国家から解放された二つの「在日」社会は共振しえたのだろう。この点では、いずれも故郷との連絡を絶たれたなかで、従来の生活圏を取り戻し自由に往来したいと望む切実な願いを共有していたことも大きい。
だが冷戦の深化に前後して、在本土沖縄人社会では内部抗争が続き、沖縄人連盟は1948年には初期の独立論的傾向を一掃し、日本復帰論に大きく転換した。当時、沖縄ではいまだ日本からの自立・自治が唱えられていた事実を考慮すると、復帰運動はむしろ本土の沖縄人から提起されたと考えられる。敗戦直後の在本土沖縄人社会が階層的にも居住地にしても雑多であるのに比べ、疎開民・引揚者の沖縄への大量帰還が完了したこの頃には、戦前から本土で立身出世を遂げた人々が連盟内のヘゲモニーを掌握し、日本への帰属こそ当然との意見が前面に出てくる。このヘゲモニーは在郷土沖縄人に対しても行使され、本土で成功した「在日の先輩」は郷土の復帰運動に強い影響力を持った。
こうした転換は、朝鮮戦争によって決定的となった。沖縄人連盟は朝鮮人連盟と同類の組織と見られることを恐れ、やがて沖縄連盟へと改称した。また在本土・在郷土を問わず、復帰運動が活発になると、「内地」「日本」が「本土」「祖国」へ、「在日」「沖縄人」が「在本土県人」へというように名称が変更されていく。ここでも同時期の朝鮮人に対する差別・抑圧を意識した沖縄人の必死の言動が、「沖縄人」という語に湛えられた自己の固有性を切り捨てさせ、両者の断絶を深める結果となった。
複数の「在日」が、在日朝鮮人と同一視されるようになるのはいつのことだろうか。この点を深めるには、1950年代の日本社会の動向を視野に入れる必要がある。朝鮮戦争の衝撃、日本「独立」前後の逆コースと排外主義の高潮によって、50年代前半までに、この二つの「在日」社会は、いわばまったく逆の方向で「祖国」を求めるようになる。誤解を恐れずに整理すれば、朝鮮人は朝鮮半島の「祖国」(ただし二つに分断された状態の)を志向し、沖縄人は日本本土を「祖国」として復帰すべき地と選んだ。この対照には、沖縄人と朝鮮人が日本帝国に包摂され支配された近代以来の経験の相違が反映している。しかもいずれの志向も、戦後日本社会が「帝国」の経験と責任を忘却し、「単一民族」として自足するためには好都合な条件だった点は、特に強調しておきたい。
一国史的に閉域化したかに見えた日本社会が、内部から異質性を突きつけられたのは、1960年代後半以降の様々な社会運動やマイノリティからの異議申し立てとの直面によってである。このとき、二つの「在日」社会は微妙に共振する。
その契機は、〈戦場後/占領下〉の沖縄からやってくる留学生や集団就職の若者の流入によって、在本土沖縄人社会が変化と葛藤を経験する点に求められる。彼ら新しい移民は、沖縄から「立派な日本人」であることを証明するという使命を帯びて送り出されながらも、すでに成功している在本土沖縄人からは言語・生活習慣を厳しく査定されて、「県人として恥ずかしい」と批判された。こうした「立派な日本人」であるためには「立派な県人」でなければならないという二重の負荷と矛盾に直面するなかから、日本への同化とは異なる道を探る試みが生まれる。本土で生まれ成長した沖縄人の若者と集団就職で渡日した郷土出身の若者とが共同で、沖縄の伝統芸能の復活・普及をはかったり、就職差別に対する訴訟支援などの運動に乗り出す経験を通じて、沖縄人社会は新たな質を獲得していく。
また60年代後半、沖縄人の復帰への意志を収奪するかたちですすめられる日米政府の返還交渉への批判から、沖縄人自身の同化志向を抉りだし、自立を求めようとする思想が現れた。このときフランツ・ファノン等の著作とともに参照されたのが、在日朝鮮人が精神的な脱植民地化を求める苦闘を表現した同時代の作品や主張だった。たとえば復帰運動の中核たる教員でありながら運動を内部から批判し続けた儀間進は、朝鮮人が自己の「内なる日本」を「半日本人」(パンチョッパリ)として形象化した作品に衝撃を受け、自分たちもまた「半日本人」ではなかったかと自問する。儀間の思考が貴重なのは、この発見を自ら成長させ、沖縄人の日本への同化を批判するだけでなく、さらにすすんで、在日朝鮮人・被差別部落などへの差別と沖縄への差別とに共通する日本社会の構造を見抜いた点にある。しかも彼の場合、在日朝鮮人の作品を参照する契機に、戦時中九州に疎開した際の朝鮮人との出会いを想起する場面があったことは注目されてよい。
日本社会におけるこの二つの「社会」(閉鎖的・空間的な領域を指しているのではない)は、戦前以来の厳しい関係を含みつつも、帝国崩壊と冷戦の進行を受けた屈折をへて、今日に至る。もちろん、この二つの社会を過度に相似的なものとみなしたり、それぞれの社会内の容赦ない対立や亀裂をも含んだ多様性を無視するわけにはいかない。しかし、沖縄人と朝鮮人の歴史的経験を分断し、その関係を見えないものにしてきた歴史観がある以上、この両者の「戦後」のあり方に、認識上の「橋を架ける」試みが求められている。沖縄史を考えるにも、「日本と沖縄」という二者関係に緊縛された認識を超えるには、在日朝鮮人との関係のあり方を、たとえ時に酷薄な断絶をともなったかぼそい線であっても、それを「関係」として見出し、たどり直す試みが、今後いっそう要請されるだろう。そのとき、「在日」という言葉がたどった歴史性は、様々な分断を越えて被差別民衆関係史を展望するための有効な糧となるのではないだろうか。
2003年3月15日に立教大学で開催された第3回研究会は、全体テーマを「戦後日本のなかの”エスニシティ”」と表題され、小林知子氏(福岡教育大学)「在日朝鮮人の『多様化』の一背景」、戸邊秀明氏(早稲田大学・院)「(戦場後/占領下)社会と複数の『沖縄人』」の2本、コメンテーターは安田常雄氏(電気通信大)と中野聡氏(一橋大)であった。研究会の状況を報告する筆者の心覚えのため、また研究会に参加できなかった方々のために、お二人の報告内容の概況をお知らせした上で、気づいた問題を記させていただくことにしたい。
小林氏は、年来取り組んでこられている在日朝鮮人問題を、その意識の多様化の形成をどのように捉えるかを中心として報告した。氏によれば、まず在日朝鮮人の形成史のなかから、第二次大戦前の状況、戦争直後の運動化の時代、朝鮮戦争とサンフランシスコ講和の時代、そして冷戦体制の中での朝鮮半島の分断とその下での意識形成などを、明解に論じた。氏は在日朝鮮人を「日本のマイノリティ」、「エスニシティ」と規定するのでは、充分に問題状況を把握することは困難であるとの認識に立っている。むしろ「在日」と「朝鮮半島」との関連で捉えることの意味を重視する。
戦前、朝鮮人はいわば日本帝国主義による「強制的拡散」の中で、特殊な位置を占めたこと、戦後は日本の敗戦を契機に、「残留」(後に意識された「在日」とはやや趣を異にしよう)朝鮮人、そして何よりも「朝鮮民族」としての自覚を促す状況が創り出された。在日朝鮮人連盟は当初、冷戦体制の形成とは無縁に、朝鮮人全体をカバーする組織としての論理を内包していたこと、新朝鮮建設への共通の意識の下で諸課題に取り組むという点で、朝鮮半島との連帯意識は当然であったと考えられる。しかし朝鮮戦争を経過する中で、在日朝鮮人と祖国「朝鮮半島」との分断、さらに南北分断による「在日」の分断という二重の分断構造を余儀なくされる。しかも日本政府は国籍条項でも「朝鮮籍」についての否定を通じて、一方的立場に与する結果を招き、周知のように朝鮮人連盟は、在日朝鮮人総連合会と在日韓国居留民団へと(解体・)分解されてゆく。いわば「生活圏」そのものの決定的分断が形成され、「在日」日本人との連帯の筋道も見あたらない状況となった。
この状況に変化をもたらし始めたのは冷戦の展開の下で形成されてきた生活基盤としての日本列島内部での民族差別撤廃要求運動、朝鮮統一をめざす動きなどは、朝鮮民族としての「生活圏」遮断に対する抵抗としての意味を持つとした。「日本社会に生きている朝鮮人」、「祖国志向」、「他国人との共生社会形成」の三様の意識が在日朝鮮人の中に存在する。と同時に在日朝鮮人の形成には植民地支配政策と冷戦体制の問題があることを記憶として共有することが求められると締めくくった。
まず「沖縄人」の定義、「琉球人」の意味が問題となる。沖縄の人自らが名乗る「沖縄人」と他者の定義する「沖縄人」がいかに異なるか。当然、前者は誇りを持つものであるのに対して、後者は蔑視観によって裏打ちされていると見るのは、言い過ぎであろうか。「戦後日本」の枠組みでは、沖縄は見えない。ジョン・ダワー『敗北を抱きしめて』がその好例という。ついでながら、「本土」の経済成長信仰にとっても、沖縄は意識されない存在であったことは言うまでもない。「沖縄人」定義も複数化している。すなわち「在本土沖縄人」という定義もあり得ること。分断・亀裂を明るみに出す上で、「沖縄人」定義に意味がある。ちょうど在日朝鮮人定義との対比も必要だという。
戦前の「沖縄人」は、日本帝国への併呑による序列化の面と他の植民地支配との相違性を把握する、あるいは「沖縄人は他の植民地人とは異なる」との認識。「南方における指導者としての沖縄人」意識とその現実的挫折(これはちょうど日本民族が世界の指導者ばりで推進された大東亜共栄圏から八紘一宇へのロジックの、同心円的な、あるいは沖縄的な表現とも言えようか)。敗戦時の場合、「在本土沖縄人」の多様な社会層が形成されていたこと。また沖縄では「戦場後」の意識としての「戦争責任」のありよう、「沖縄戦」との距離感(現場に居合わせた沖縄人かそうではない沖縄人、そしてそれらと無縁の「本土」人)が意識のズレを招いてきた。
占領下、沖縄の本土との物理的隔離・分断、民衆にとっては「復帰」が重視されねばならないこと(筆者の目からすると、まさに沖縄体験は幾重にも本土の人々とは異相を形成している点も注意すべきことであろう)。本土占領下の沖縄人連盟、「解放」の夢破る米軍支配の実相の中で、復帰運動の意味の複雑性があること。それも沖縄における場合と本土の場合には大きな隔たりを持つこと(たとえば、沖縄県民にとっては「復帰」運動が日本国憲法治下に自らを置くことで、米軍支配から離脱する契機を持とうとした。しかし本土にとっては、その意味が十分にとらえれていたとは言い難い。すなわち本土の米軍従属的構造からの離脱をも前提にした取り組みなしには、沖縄県民の本来の願いを達成できないと言うことであろう)。在日沖縄人→在本土県民への転換、部落問題と沖縄問題(もちろんその等視はできないし、またそうすべきではないだろう)。「脱帝国」の視点から沖縄人をどのように考えるか?など。「在本土沖縄人」と「在沖縄沖縄人」、この点で「在日朝鮮人」「在朝鮮半島朝鮮人」の対比が必要である。彼等にとっての「祖国」の物語とは一体何であろうか。
筆者にとって興味あるのは、安田、中野氏2人のコメントとの関連で、果たしてアメリカで展開されたエスニシティ研究と、「在日」朝鮮人・沖縄人問題をどのような異相において捉えるかという点が第一。筆者には公民権運動の中から形成され始めたマイノリティ問題、そしてエスニシティ問題は、「アメリカ帝国」の枠組みの政治的に包摂された多様なエスニックグループの中でも歴史的にもっとも抑圧を受けてきたブラックと朝鮮人問題が類似しているように見えるが、実は大きな異相を持っていることに注目したい。そもそも「近代市民革命」としての「独立戦争」を経験したアメリカにとって、ブラックは奴隷制を不可欠の一環としての工業化を実現していった事実が重視されねばならず、いわば資本主義は奴隷制とともに歩んでいった点で、アメリカのホワイト市民にとっての抑圧対象としてのブラックであったこと。朝鮮人はこの面では、資本主義労働市場の原理によって形成された「国境を超えた」底辺労働力としての在日朝鮮人であり、ブラックの場合とは位置関係を異にしていたはずであろう。
なおアメリカのマイノリティ運動にとって不可欠の要素は、在米日系人の太平洋戦争期における収容所問題と、1988年にまで繰り延べされてきたその補償であろう。筆者がNIKKEI2000のサンフランシスコシンポジウムに参加した際に、日系人報告者がフロアからのドイツ系アメリカンの「日系人はブラッドの問題として意識しているのか、それともアメリカ市民社会のありようとの関連で課題を突き詰めようとしているのか」との真っ当な質問に対して、「私たちは民族性の問題としてではなく、アメリカにおけるマイノリティ問題の解決、アメリカ市民社会の民主性を支える課題として、日系人問題を扱っている」との回答に、思わず、在日日本人の私は、彼らの偉大な成長を認識させられたのである。
このことは、単純にまさに沖縄の人々の本土でのありようとアメリカのマイノリティを同等視してはならない、問題性をはらんでいると思われる。ある意味では在日朝鮮人の場合でも、植民地支配を前提として流入した朝鮮人労働力の定着を基盤とした今日の状況は、民族的多様性によって形成されてきたアメリカにおけるマイノリティ問題とも異相を持つことを自覚すべきであろう。外見的にはアメリカで形成されたマイノリティ研究の状況とも類似しているようでいて、やはり異相を見失うこともできない。そこに報告者の言う歴史的過去を忘れるべきではないという意味の重要性があろう。
第二に、在日朝鮮人と「在本土」沖縄人の関係は、前者は民族的差別性を前提とした底辺労働力を形成したに際して、後者は「外見的」には「日本人」として扱われながらも、差別化された底辺労働力を形成したということ。むろん研究会でも指摘されていたように、場合によっては朝鮮人よりも沖縄人の方がより冷遇された労働条件に位置づけられたこともあり得た。また沖縄戦では、本土兵から差別化された沖縄兵が歴然たる事実でもあった。沖縄は北海道と同様に「内国植民地」として中央資本・政府の収奪対象であったことは疑いをいれない。現に1925年の帝国経済会議植民部会は、そのように位置づけ「本土」住民の植民を図るとし、それによって経済振興策を提示しようとしていた(山本義彦編『第一次大戦後経済社会政策資料集』全8巻、柏書房、1987年)。この面では朝鮮人に対する支配のあり方とは異相を形成したのである。
第三に、安田氏の指摘した「故郷」と「祖国」の関係。抽象的論議では「朝鮮人」にとっての「祖国」とは「朝鮮半島」と言いうるが、これはあくまでも論理的抽象となる。つまり長年にわたって「在日」状況にある「朝鮮人」にとっての「祖国」は「故郷」と同様に、今彼/彼女が暮らしている場所と同義であろう。理念・観念としてはたとえ「朝鮮本土」が「祖国」であるにせよ。それは在米日系人2世、3世を考えればよいであろう。要するに人間にとっての「祖国」、「故郷」は、想像可能な空間でしかあり得ないのではないか。安田氏のいう「ひとりひとりの暮らし」の領域こそが「祖国」や「故郷」を想定できる幅かも知れない。
第四に、中野氏の指摘に関わるが、アメリカではホワイトネス指向性がそれぞれのエスニックグループのありようを規定してきたというが、この説に倣って言えば、朝鮮人軍人が「皇国民化」を競って成績を挙げようとした卑屈ではあるが理解可能な事実があり、同様に見えるのは沖縄出身の兵士が本土決戦下、本土兵によって抑圧された中で、より「皇国民」として生きようとする「誠実さ」を示したことであろう。それはちょうど日系二世が太平洋戦争に際して競って軍隊に参加し、武功を競うことで、アメリカ国家に「忠誠」を誓おうとした事実にも相似する。これらもいわばアメリカのホワトネス(whiteness)化に類比が可能であろう。
2002年4月に開催された同時代史学会準備大会および同年12月の創立大会の報告等を中心に編集した『戦争と平和の同時代史』が今秋に日本経済評論社から刊行される予定です(価格未定)。
目 次
第1部 澤地久枝と同時代史を語る
第2部 同時代史の中の戦争
第3部 サンフランシスコ講和50周年を考える
第4部 同時代史の方法
1950(昭和25)年3月17日から6月11日まで、兵庫県西宮市において「アメリカ博覧会」が開催された。この博覧会は朝日新聞社によって主催されたのであるが、その趣旨は「アメリカのあらゆる面をよく研究し、検討することは、今日のわれわれにとってよき参考または反省の資料を提供するものと信じて疑わない」(朝日新聞社社長・長谷部忠)ということだった。連日の宣伝により、200万人を越える入場者を記録し、占領期における巨大な「メディア・イベント」であった。
アメリカ博覧会については、すでに津金澤聡廣による詳細な研究がある(津金澤聡廣「朝日新聞社の『アメリカ博覧会』」同編著『戦後日本のメディア・イベント』世界思想社、2002年)。それによれば、「観客動員二〇〇万人の成功をおさめた『アメリカ博』はまさに、GHQの占領政策と『朝日新聞』の文化戦略との合作による占領期を象徴するアメリカニゼーション推進の祝祭であった」。
アメリカ博覧会がもたらした効果を示す資料としては、アメリカ博覧会終了後に刊行された図録(平井常次郎編『アメリカ博覧会』朝日新聞社、1950年)に収録された「学生エッセイ・コンテスト」の優秀論文がある。しかし、これは、「いずれも観客反応の一面ではあるのだが、あまりに審査員の狙いどおりの作文」(津金澤、前掲論文)であった。また、岩本茂樹も、『戦後アメリカニゼーションの原風景 -『ブロンディ』と投影されたアメリカ像-』(ハーベスト社、2002年)のなかで、この博覧会について述べているが、そこでも同じ資料を用いている。しかし、この作文は、あまりに模範的にすぎ、実際の入場者の意識をどれだけ反映しているのかについては疑問がある。入場者が、実際にどのような展示物に心を動かされ、またそれによって、当時の日本人のアメリカニゼーションがどの程度進んだのかということについては、さらに分析を進める必要があろう。
博覧会開催期間中、朝日新聞社世論調査部は、A.一般調査、すなわち大阪・京都・兵庫の3府県でサンプル数2175の世論調査と、B.特別調査、すなわち5月12~18日の入場者の中から、大阪・京都・兵庫の3府県の居住者1000人を対象とした調査を行った。こうした博覧会では、入場者を対象としたアンケート調査はよく行われるが、比較対照のために非入場者に対する世論調査も行った点で、この調査結果は非常に興味深いものである。そこで、GHQ/SCAP資料の中にあるその報告書(の草稿?)を用いて、アメリカ博覧会の効果について分析し、当時の日本人が抱いていたアメリカ観や、博覧会がアメリカニゼーションに果たした意義について検討してみたい。
質問項目は多岐にわたっており、両者の比較からは多くの知見が得られたが、ここではその中から特に興味深いものを紹介したい。
まず、「博覧会を見に行く気になった理由」では、「アメリカを知るため」が1位の28%で、つづいて「めずらしがり、話の種に、漠然とした関心、レクリエーション」(22%)、「宣伝、前売券を買った、評判にひかれて」(21%)などとなっている。報告書は、「以上、さして深い理由のないものが多く占めている点からみて、必ずしも博覧会が人々の知識の源泉としての対象になっている訳でなく、リクリエーションを兼ねた一日の行楽をここに求めた人々が多いと推察されるにすぎない」と分析している。
他方、非入場者が見に行かない理由としては、「家庭の事情、多忙」(50%)がトップで、「特に、郡部、就中農漁業に多い」という。表1は、入場者と非入場者の特性を比較したものである。独立性の検定をしてみると、「女性」より「男性」、「低学歴」より「高学歴」、「先月中にアメリカ映画を見ない」人より「見た」人、「英語を読んだり話したりできない」人より「できる」人のほうが博覧会を訪れたことがわかる。
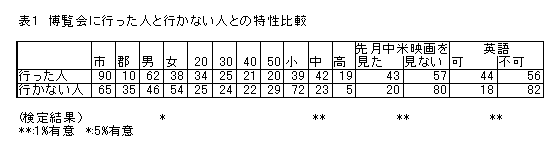
しかし、非入場者であっても、「アメリカ博覧会を開催したことはよかった」と答えた人は全体の6割に達し、その傾向は、特に若い世代、高学歴の人々に顕著に見られる(表2)。
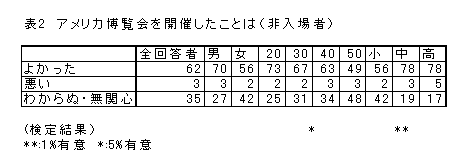
次に、入場者の感想をみてみると、博覧会が「一番人々に印象を与えたもの」では、「パノラマ」が52%で、次の「規模の大きさ」(23%)を大きく引き離していた。「一番気に入った陳列品」は、「日常生活(台所設備・シンガーミシン・服地・家具)」(13%)、「パノラマ」(13%)、「計算機・機械・タイプライター」(12%)などとなっている。また、「一番時間をかけてみた陳列品」は、「パノラマ」(15%)、「日常生活」(10%)、「新日本産業館」(8%)、「計算機・機械・タイプライター」(6%)などとなっている。これについて、報告書は、「要するにすべての陳列品の中で「日常生活」と「パノラマ」が人々の関心を他にぬきんでて惹きつけたと考えて誤りはなかろう」と述べている。
また、「博覧会によってアメリカが理解できたか」という問いに対しては、「理解できたと思う」が50%、「思わぬ」が34%であったが、「日本の改善にすぐに利用できるものがありますか」という問いに対しては、「利用できるものあり」は44%で、「なし」が23%、「分らぬ」が33%となっていた。また、アメリカに対する好悪に関しては、博覧会に行った人々のうち50%が「アメリカを好き」と答えているが、「博覧会を見てアメリカが好きになりましたか、きらいになりましたか」という問いでは、「好きになった」は17%にとどまり、「変らない」が80%に達している。
この調査結果を見ると、当時、確かにアメリカに対する関心が高く、それゆえアメリカ博覧会に多くの人々が来場したと言える。そうしたアメリカに対する興味・関心は、若い世代、高学歴層、そして英語の能力がある人に強いようであり、属性や階層による差異があったことがうかがわれる。
その一方で、人々の関心を引いたのは、アメリカの文物や風習だけではなかった。むしろ、「パノラマ」といった展示物そのものに対するもの珍しさ、すなわち「見せ物」としての魅力にひかれて訪れた人々も少なくなかったと思われる。このように、受け手が持つさまざまな欲求の中で、「アメリカ」は受容されていったのだと考えることができよう。
また、アメリカに対する「まなざし」は、まずは台所設備・シンガーミシン・服地・家具・計算機・機械・タイプライターといったモノや機械に向けられていた。そしてそこから次第に、そこに通底する「合理主義」「豊かさ」「科学文明」といった精神や価値観を受容していったのだと考えられる。
付記 当日、コメンテーター務められた有山輝雄先生をはじめ、会場の多くの方から有益なコメントを頂戴しました。あらためて感謝の言葉を申し上げます。
本報告が考察対象とする10年間は、米ソ両国政府が、核軍備競争の結果として生まれつつあった相互核抑止状況の下で、野放図な核兵器開発を抑制し、核兵器と共存するための方策を模索し始めた時期であった。1963年に最初の核軍備管理条約として成立した部分的核実験禁止条約は、その成果のひとつである。
しかし、その背後要因として、当時、核兵器の実験・製造・貯蔵・使用の禁止を求める国際世論が強まるなか、反核兵器運動が世界各地で盛り上がりをみせていた事実も無視し得ない。日本国内でも、この頃、1954年3月のビキニ事件を契機として、核兵器を忌避する国民世論が醸成され、そのような世論の広がりのなかから誕生した原水爆禁止運動が、やがて「国民運動」と呼ばれるまでに成長していったことは周知の事実である。
このような当時の状況を振り返ると、日米間では核兵器との共存の可能性に関して相反する2つの立場のせめぎあいがみられたといえる。すなわち、一方では米国政府が、核兵器が戦争を起こすわけではなく、むしろ核兵器は戦争防止に有効な手段であるとの立場から、核兵器との共存を模索していた。他方で、核兵器開発競争は国際関係を悪化させ、究極的には核戦争を惹き起こし、人類破滅の危険をもたらすとの認識に基づき、核兵器との共存を否定する傾向が日本の原水禁運動にはみられたのである。
以上のような時代状況認識から出発して、本報告では、最初に、核兵器に対する人々の恐怖心や反核感情に対するアイゼンハワー政権の対応について、次に、日本国内の核兵器を忌避する国民感情や原水禁運動に対する日米両国政府の対応と、その裏にあった状況認識や政治的意図について検証する。そして最後に、1960年代に入っても、米ソ両国を中心として核軍備競争が続けられ、世界が核兵器との共存の道を突き進むという現実に、日本の政府と原水禁運動がいかに対峙していたかについて考察したい。
アイゼンハワー政権は1953年1月に発足すると、対ソ封じ込め戦略の見直しを図り、財政的コストの大きい通常兵力の削減を推し進め、当時、米国がソ連に対して圧倒的な優位にあった核兵器を軍事的封じ込めの手段として重視するニュールック戦略を採用した。1954年にはダレス国務長官が大量報復戦略を発表するが、これは、ソ連・共産主義勢力が戦争を仕掛けてきた場合、それが通常兵力によるものであれ、報復手段として核兵器を使用することを前提とした核抑止戦略であった。
ところが当時、朝鮮戦争を契機として冷戦のグローバル化と軍事化が進展し、米ソ両国が相次いで水爆開発に成功するに及んで、核兵器や核戦争に対する人々の恐怖心が世界的に広がっていた。アイゼンハワーやダレスにとって、このような国際世論は、核兵器の使用を前提とする大量報復戦略に対する障害にほかならなかった。しかも、同盟諸国の世論にみられる核兵器や核戦争に対する恐怖心や反核感情は、同盟国の中立傾向や対ソ宥和姿勢を強め、西側陣営の結束を弱めかねない、という意味でも懸念すべきものとなっていた。
そこで、アイゼンハワー政権がとったのは次のような対応であった。第一に、1953年12月にアイゼンハワーが国連総会で行った「平和のための原子力」演説を口火として、海外における原子力平和利用に関する啓発活動や、原子力平和利用分野における国際協力を推進した。そのような活動を通じて核兵器に対する人々の恐怖心が和らぐことへの期待が、米国政府部内や軍部にはあった。
第二に、同盟諸国政府から米国の軍事戦略に対する理解を得る努力が続けられた。核兵器は西側自由主義陣営の兵力の不可欠な一部であり、核兵器の使用が必要なときには、迅速かつ選択的に使用しなければならないことを、否定できない現実として受け入れさせることが狙いであった。アイゼンハワー政権時代、NATOが西欧諸国の防衛を米国の核兵器に依存する傾向を強めたのは、ニュールック戦略が西欧同盟諸国に受容され、NATO戦略に適用された結果であった。
このような対応は日本に対してもとられたが、それは、アイゼンハワー政権が日本の原水禁運動や、その底流にある核兵器を忌避する国民感情を、次のような2つの観点から問題視していたからであった。
第一に、対日政策の観点からすると、日本国内の反核感情の高揚が、反米感情や中立傾向を増進させることへの警戒感があった。ビキニ事件後、米国側が日本中立化に懸念を強め、このことが対日政策見直しの政治的文脈の一つとなっていたことは、すでに従来の研究で指摘されている。
また、極東における米国の軍事戦略の観点からも、日本国内の反核感情は米国側にとって憂慮すべきものであった。日本国内には核兵器の持ち込みや、日本の核武装化に反対する世論が強かったが、ニュールック戦略の下、日本において米軍基地を確保し、核攻撃の前線基地として日本を利用することが軍事的観点からは望まれていたからである。
しかも、こうした二つの観点は必ずしも両立するものではなかった。そのためアイゼンハワー政権は、例えば核持ち込み問題に関して、対日政策の観点から日本の世論に配慮する必要と軍事戦略上の必要の折り合いをつけるため腐心しなければならなかった。その意味で、核兵器を忌避する日本の国内世論や、それを背景に発展してきた原水禁運動は、米国政府の外交・軍事戦略の運営や遂行を困難にする政治的障害となっていたといえよう。
他方、日本政府の対応をみると、核兵器問題に関する米国政府の立場に異論を唱えることなく、例えば核実験問題に関して、西側陣営の防衛にとって必要であるとの米国政府の立場に理解を示していた。その裏には、当時、日本の政治指導者が、核兵器には戦争防止の効果があり、核兵器がもたらす力の均衡によって平和が維持されている、との認識を持つようになっていたことがあった。また、外務省高官の間では、西側陣営の軍事戦略は核抑止力の必要性に基づいており、「西側陣営の一員としての立場の堅持」という日本外交の原則にそって、これを核兵器問題に関する日本の立場を考える際の前提としなければならない、との共通認識がみられた。
しかるに、日本国内の反核感情や原水禁運動への対応に関していえば、米国政府の期待とは裏腹に、米国側が望むような国内世論の形成を試みようとはしなかった。むしろ、国内世論に配慮しながら、核兵器問題に関する政府としての政策や対応を決定するというのが実情であった。それ故に、様々な核兵器問題に関して、日本政府は国内世論の圧力と、「西側陣営の一員としての立場の堅持」という外交原則との狭間で対応に苦慮することになる。
例えば、核実験禁止問題に関する日本政府の対応をみると、鳩山・岸・池田内閣は、日本国内の反核感情の高まりや原水禁運動の進展に呼応する形で、当時、核実験を繰り返していた米英ソ三国に対して抗議外交を展開したが、この抗議外交には次のような特徴があった。
第一に、国民世論が、革新勢力や左翼陣営が主導する原水禁運動に取り込まれ、世論の反核感情を政府が制御できなくなることを回避する、という国内政治的な目的が込められていた。核実験禁止に関心を持って取り組んでいる姿勢を世論に示すことにより、「国民運動」としての原水禁運動を、保守政権の影響力の及ぶ範囲に留め置こうとしたのである。そして、もう一つの特徴としては、西側陣営の一員としての立場から、核実験に対する米国の政策や西側陣営の立場に不利になるような行動を極力避けようとしていたことがあった。
つまるところ、核実験に関する日本政府の抗議外交は、国内世論と西側諸国の立場に配慮しつつ、ビキニ事件後にみられたように、核実験に関する日米両国の立場の違いが原因となって、日米関係に軋みが生じることを未然に防ぐ試みであったといえる。
1960年代に入っても、前述のように、核兵器を忌避する国民感情が核兵器問題に関する日本政府の立場を拘束する主要因であり続けた。しかし、その背後で、そのような世論が核兵器問題に関する日本政府の政策や対応に反映されにくい国内政治の構図が温存、強化されていったことは看過されてはならない。55年体制下で安保改定、高度経済成長を経て、自民党一党支配が安定化するに伴い、「西側陣営の一員としての立場の堅持」という外交原則に基づいて、核抑止力の必要性を核兵器問題に関する日本の立場を考える際の前提とする日本政府の方針が、より強固な政治的基盤に立つことになったのである。
他方、日本の原水禁運動の側には、国内世論を動員し、政府に対する政治的影響力に転換することができない事情があった。まず、日本の原水禁運動は1957年にひとつの頂点を迎えた後、「国民運動」としての性格を失っていった。55年の発足以来、原水禁運動を主導してきた原水協が、58年10月に日米間で正式交渉が開始された安保改定に反対の方針を打ち出すと、自民党は原水禁運動の左傾化、共産主義勢力の影響力の増大に批判の矛先を向け始め、原水禁運動から離脱する保守系団体も現れ始めている。
加えて、この頃から運動方針をめぐって内部対立が表面化し、最終的には原水禁運動の分裂がもたらされた。すなわち、60年代に入ると、ソ連の核実験や部分的核実験禁止条約の評価をめぐって原水協内の党派的対立が激化し、55年以降、原水協主催で毎夏開かれてきた原水禁世界大会が、63年には分裂開催されるという事態に発展した。そして、61年に民主社会党が全労と共に核禁会議を組織したのに続き、65年には原水協を離脱した社会党と総評が中心となって原水禁を発足させるに至っている。
このような運動分裂騒動は、超党派的な「国民運動」としての原水禁運動を理想化する日本のマスコミや世論の失望を買い、結局、一般市民を運動から遠ざける原因となった。原水禁運動の停滞と運動が生み出す対政府圧力の低下が、その帰結であった。
会則の付則にありますように、会計年度は4月~翌年3月となっております。少数ですが2002年度会費が未納の方がいらっしゃいます。未納の方は2年分、また2003年度会費未納の方は郵便振替にてお支払いくださいますようお願いいたします。
会費は、年額で、一般の方5000円、院生の方3000円です。
| 郵便振替 | 口座番号00120-8-169850 |
| 加入者名 | 同時代史学会 |
なお、お支払いいただいた振替用紙をもって領収証にかえさせていただきますので、ご了承ください。
また、住所などにご変更のある場合は、振替用紙にその旨をご記入ください。よろしくお願い申し上げます。
入梅も間近に迫る2003年6月7日(土)、立教大学太刀川記念館3階多目的ホールにて、第3回定例研究会(第4回研究会)が行われた。「情報と核をめぐる日米関係」という共通テーマの下、最初に井川充雄氏が「占領期におけるアメリカニゼーション -『アメリカ博覧会の効果をめぐって」、続いて黒崎輝氏が「核兵器との共存の道 -日本の原水爆禁止運動と日米関係 1954-1963」というタイトルの報告を行い、井川氏には有山輝雄氏が、黒崎氏には植村秀樹氏がそれぞれコメントを付された。司会として浅井良夫氏と斉藤伸義氏が全体の進行役を務められた。
それぞれの報告の詳細は両氏の報告概要に譲ることとし、その補足という形で各氏の報告に対するコメンテーターとフロアーからのコメントや質疑応答の様子について触れ、またそれを通じて見えてくるこの学会ならではの特徴と発展の方向について、末席を汚した新参者の私で恐縮ながら、その一端を述べさせていただきたい。
まず井川報告に対して、コメンテーターの有山氏は四点について注意を喚起された。即ち、まず「アメリカニゼーション」という概念が、果たして混沌としていた占領期時代における社会意識のダイナミズムを分析する上で有効であろうかという点、アメリカに対する好悪などの感情の問題と「アメリカニゼーション」は別であるという点、そしてアメリカ展覧会をはじめとするアメリカ側からの所謂「プロパガンダ」に対して、日本人は一方的にそのプロパガンダを消化する消極的な対象にとどまるというよりも、むしろ日本人側にもアメリカを学ぼうとする積極的な動機があったのではないかという点、最後に、報告者の分析を「日本人の『体験した』占領の分析」と高く評価しつつも、分析対象である質問票自体に内在する限界点、即ち、果たして細分化され、個別化された個々の質問ひとつの中に、本来的に重層的な「体験」を読み込むことができるのかという点を指摘された。
続いてフロアーを巻き込んだ質疑応答に移ったが、その様子はまさに同時代史学会ならではのものであった。狭い問題領域のみに特定された、馴染みのメンバー同士での研究会とは異なり、文字通り「専門分野を横断し、市民・研究者を問わず垂直性・排他性のない開かれた学会」の面目躍如とばかりに、質問された方々のプロフィールも様々ならば、その質疑も広範囲に及び、会場全体で参加して議論を尽くそうとする意欲あふれたものであった。メディア・文化史の視点から書かれた報告に対し、経済史からの視点を提起された方、アメリカ側の視点の重要性を指摘された方、そして展覧会の裏方で活躍した人々に言及し、大文字の歴史とその裏に潜む無数の歴史が交差する瞬間に眼を向けられた方など、実に多方面から多岐に渡る指摘やコメントがあり、さながら本学会の「複眼思考」性を象徴する情景であった。特に私の印象に深く残ったのは、実際に占領期を同時代として生き抜き、朝日新聞の調査資料部長としてご活躍されたOBの方が、宣伝における地域差の問題や検閲の可能性などを指摘されたコメントである。ともすれば外部の視点からでは注意が行き届かない点に、分析の鍵が潜んでいる場合がしばしばある。そのような部分に眼を向ける契機となる「内部の視点」を提供してくださるこのような方々との質疑応答は、報告者のみならず若手の私も含めて参加者各自も学ぶところが多いのではないだろうか。まさに「市民に開かれた学会」に参加するからこそ享受できるメリットのひとつといえるだろう。
続いて黒崎報告に対してコメンテーターの植村氏は、運動主体と日米両政府という三つ巴の相互作用のダイナミズムを、日米関係史という統一された文脈上で分析するという報告者の着想を高く評価しつつ、今後の分析を待つ幾つかの可能性について言及された。特に、報告者が分析上の理念形として提示した「党派性⇔無色透明」「核兵器の拒絶⇔共存」といった二項対立的なキーワードについて、植村氏は「共存」の含む意味を論じつつ、その両極の間、もしくは彼方に広がっているフィールドや選択肢の豊穣さについて指摘された。そして資料的制約・問題の同時代性などの諸要素により従来は困難とされてきた核問題の実証分析を今後進めていく上で報告者が提示した「歴史のイフに挑戦する“思考実験”」について植村氏は、報告者が想定しているような日本政府側の認識形成過程を解明する際に新たな突破口を開くのみならず、原水爆禁止運動側のダイナミズムの新視角ともなりうると述べ、今後の研究の発展を期待してコメントを締めくくられた。
その後フロアーからは、1963年に締結された部分的核実験禁止条約などに見られる、核兵器との共存問題における”the middle of the road”的なオプションを模索する国際的な動向と日米両政府の対応との関連についての質問や、被爆者を被験者として日米両国が共同して研究した例を指摘し、占領期から一貫して続いている日米両政府の説明責任の欠落を厳しく指摘する声、沖縄返還との関係や国内および国際動向と日本の国連での核兵器禁止問題についての投票行動との連関を問うコメント、「反核運動」の戦略と目的が核戦略の洗練化に遅れをとっていたとの指摘など、活発な意見や提言が開陳された。
研究会全体を振り返ってみると、まだ運営や進行は手探り状態とはいうものの、随所に目指すべき新たな学会像を垣間見ることができた。長年その問題と共に生き、考え抜いてきた方々や、実際にその時代を「同時代」として体験し、歴史の証人となった方々などが、市民、研究者の垣根を越え、専門分野を越え、年齢・性差を越えて、今ここに「同時代」を捉え直す知の基盤を作り上げようという意欲に満ちて今ここに集っている。特に私のような若手研究者にとっては、従来の学会に付き物であった垂直性(hierarchy)を打破し、「同時代」を生き抜き、絶えず知的挑戦を続ける同志・同僚(colleague)として、多様な関心と専門分野を横断した双方向型の交流の場を提供しようとする本学会への期待は大きい。
ただ、目指すものが大きい分だけ、報告者を含めた参加者全員の協同と創意工夫が求められよう。従来の学会とは異なり、これほど多様な専門分野や問題関心、年齢・性差・職業的背景をもった人々が集っているのであるから、報告と討論の中でこの長所を最大限に引き出さない手はない。例えば、報告者側が自らの分析視角を更に明確にし、事前にどのような点について他分野の方々とも議論を深めたいのかを示唆することで、ともすれば関係の希薄な分野からの活発な発言を誘発する間口を広げることができるかもしれない。参加者側も、「同時代」を考えるという広い問題意識を念頭に、報告分野以外の人々の発言を促しつつ、当該分野における議論も深めるような形での参加や進行を試みたらどうであろうか。極度に細分化され、もはや学会の外との共通のボキャブラリーを喪失した(そしてそのことに対して一種の優越感さえ覚える)学会が山積している昨今、今こそ本学会のような専門分野・年齢・性差・職業等を横断し、市井の視線に徹する新たな学会が必要とされている。今後は従来の学会の域を真に脱するべく、研究会自体を一つの知的実験として、このような「方法論」の開発にも取り組んではいかがであろうか。
| 日時: | 2003年11月1日(土) 14時~17時 |
|---|---|
| 場所: | 立教大学 12号館地下第1・第2会議室 |
| テーマ: | 戦後民主主義 -運動と思想- |
| 報告1 | 和田 悠(慶応義塾大学大学院博士課程) 「松田道雄の育児論にみる思想としての『戦後民主主義』」 |
| 報告2 | 武居 秀樹(中央大学経済学部非常勤講師) 「戦後史における革新自治体の歴史的位置の検討 -美濃部東京都政を事例に-」 |
| コメンテーター: | 中西新太郎(横浜市立大学) 安達 智則(東京自治問題研究所常任理事) |
最近、同時代史に関わる着目した研究業績は、青森県の『東奥日報』記者、斉藤光政氏の『米軍「秘密」基地ミサワ 核と情報戦の真実』(同時代社、2002年)である。縄文の三内丸山遺跡などと並行して、在日米軍・三沢基地を取材した。旧ソ連・中国・北朝鮮に向けた「槍の矛先」であり、現在はイラクへの監視飛行から3月開戦の先制攻撃を担った。今年5月に斉藤光政氏を鹿児島県姶良郡の地域労組による憲法講演会に招いた。
同氏によれば、1962年のキューバ危機の際は、日本国民の知らぬまま世界戦争前夜となり、駐日大使・ライシャワーと在日米軍指令官が東京から逃れて青森・三沢に来ている。また、1973年のミッドウェーの横須賀母港化が沖縄やついで韓国からの核兵器<核物質(core)と起爆部(component)からなる>引揚に伴う代替措置で、米軍には兵器本体は常時あり、緊急時にはグアム、ハワイなどから核物質を持込み、組み立てる態勢にあることなど紹介があった。日米安保条約下での「核疑惑」「有事持込」の意味が解けた。〔ほかにも1968年の北朝鮮による元山沖、プエブロ号拿捕の際、在韓米軍・鳥山のF4攻撃機が核攻撃仕様であり、通常爆弾を装填できぬ「不手際」にも言及〕
斉藤氏は、数年で情報公開法(FOIA)や米国での聞き取りを通じて、以上の事実を解いた。青森県三沢という地域と現代史の接点を見事に捉えた事例である。札幌の米国領事館がワシントンに報告、「解明した事項は正しい、米国で研究しないか」と招請までしているからさらに驚く。以下は、九州での研究活動の紹介である。
熊本での近代史研究会は、1960年の安保闘争を機に「東アジアと九州の地域」を歴史的に捉えようと高校、大学の教員から発足、毎月の定例会が40年を越えた。会誌購読者が会員で60名弱、市民会館での例会は14、5名で学生、院生、専業主婦、元新聞記者、農業指導員、現職や退職の中学・高校・大学の教員、元労働運動家、作家、編集者などである。熊本、福岡、鹿児島などの幕末から近代史、戦後史を毎月、交代で発表、意見交換しあう。同時代史では、熊本県球磨郡の満州開拓団移民や基地反対闘争の聞き取り報告があった。毎月の会報(12頁)を大牟田在住の新藤東洋男氏が、会誌の発送作業は、例会の前に全員で行う。会務の事務局は熊本市の水野公寿氏が担う。数年ごとの会誌発行は、会員の出版編集者が担当する。報告後の二次会がまた、丁々発止のやりとりで知的な刺激となる。
鹿児島県では、本格的な県史は戦前に出たのみで、戦後の編纂は増補的にしか行われていない。県の史料編纂室はあるが主に近世の藩政史までの扱いである。こうした現状を変えようと1994年に阿部恒久氏(現共立女子大、近代史)の呼びかけで「史(ふみ)の会」が発足、事務局を柳原敏昭氏(現東北大、中世史)が担う。平井一臣氏(鹿児島大学、近代政治史)が継ぎ、97、8年には年1回となった。2002年からは、鹿児島近現代史研究会に改称、近代史3本と戦後史1本に分担、計4回の例会が目標。現在は5回目、会員の近業紹介が主で鹿児島の事例は2報告。
同時代史研究会に創立準備から参加した一人として期待したのは、専門研究者に限られない、市民、学生、新聞・出版、法曹、歴史教育などの複数の視点での同時代史への関心、研究、意見交換の場であった。熊本の事例が示すように、何よりも定例的な会合と会報、事務局体制である。(2003年8月24日)
本号では、前号で紹介した時点以降、すなわち2003年4月から2003年9月までの本学会のあゆみを、学会理事会での検討事項を中心に紹介したい。
理事会は、2003年4月22日、6月7日、7月11日、9月11日に開催された。前号で述べたように、2003年3月15日の第4回理事会において、大会委員会、ニューズレター委員会、研究会委員会、会員拡大委員会、企画・会誌委員会、事務局という5委員会・1事務局体制をとることが決定され、以後、理事会はこの体制の下で運営されることとなった。各委員会は、理事が複数の委員会に所属することとし、それぞれの責任者は、当面本年12月までの期間について、中野(大会委員会)、宮崎(ニューズレター委員会)、浅井(研究会委員会)、森(企画・会誌委員会)、福永(会員拡大委員会)、伊藤(事務局)が、担当することとなった。また、会則8条3項に基づいて副代表の選出が行われ、福永理事、伊藤理事の2名が副代表となった。
大会委員会では、本年度大会の企画の検討が、以下のような問題関心から進められた。すなわち、創立大会での共通テーマ「戦争と平和の同時代史」を引き継ぎつつ、イラク戦争・「戦後」占領における米ブッシュ政権の、「外部の力」(戦争と占領)によるデモクラシー実現の正当性と実現可能性という言説を批判的に検討することが現在急務であること、その際、従来の第二次世界大戦後占領史、日本戦後史における冷戦研究的な位置づけを超えて、戦後日本の実態をデモクラシー論として再構築することが要請されていること、である。いいかえると、これまでデモクラシー論は、ポスト冷戦の政治学や現代史研究で最も注目された主題のひとつであったが、その研究対象は、冷戦後期に東西両陣営の周辺諸国で展開した民主化現象に関心が集中して、いわば冷戦研究的な位置づけが強かった。このため、戦後占領研究は、必ずしもデモクラシー論そのものの視点からは本格的に検討されてきたとはいえない。とりわけブッシュ政権の一連の行動と言説を考えるならば、イラク戦争をふまえた、占領史に焦点をおいたデモクラシー研究は、今まさに求められている課題である。大会委員会の、こうした提起に基づいて、種々議論が重ねられ、本年度大会のテーマは、「占領とデモクラシー」とすること、このテーマに基づき、午前中は「地域における占領と民主化」として、戦後占領の実証的分析を行い、午後は「『戦後デモクラシー論』再考」として、今日的問題関心を柱としたシンポジウムを行うことが決まった。プログラムの詳細については、本ニューズレターの大会案内を参照されたい。
ニューズレター委員会は、これまで予定通り年2回の刊行を実現してきた実績を継続すること、内容を多面化・豊富化することが確認され、これまでの内容に加え、理事によるリレー執筆、海外便りなどを新たに掲載することとし、予定通り本号の刊行にいたった。研究会委員会も、これまで開催してきた研究会を途切れることなく、定期的に開催することに努め、6月7日に第4回の定例研究会を39名の参加で開催することができた。また、11月1日に第5回定例研究会を開催することも確定した。第4回定例研究会、第5回定例研究会については、本ニューズレターに報告と参加記および開催予定プログラムを掲載しているので、そちらを参照されたい。また、定例研究会の内容を充実するため、院生委員を置くこと、会計より年5万円を支出することが決定され、5名の院生委員が承認された。
企画・会誌委員会では、創立準備大会、創立大会の記録の出版がめざされ、日本経済評論社より、大会報告集として出版することが確定した。現在、編集作業が進行中であり、内容については、本ニューズレターの刊行案内を参照されたい。会員拡大委員会の設置は、早期に学会誌の発行を目指すこと、そのためには会員の拡大が急務であることがあることが確認されたためである。会員は継続的に増加しているが、学会誌の発行を実現するにはなお力量不足であり、今後、一層の会員の拡大が期待されている。事務局では、理事会の定期開催、他学会・他研究会との連絡、会員・会計関連事務、広報などの円滑な遂行に努めた。学会Web Site (http://jachs.hp.infoseek.co.jp/)については、6月以降非公式ながら公開を開始した。また、6月6日に会計監査を実施し、適正な内容である旨の監査報告を受けた。これらについては、本ニューズレターの関連項目を参照していただきたいが、詳細は、本年12月の年次会員総会で報告する予定である。
繰り返しになるが、本年度年次大会は、2003年12月7日(日)、法政大学市ヶ谷校舎ボアソナード・タワー26階スカイホールで開催される。会員の皆さんの積極的参加を期待するとともに、会員外の方にもプログラムを知らせ、大会参加を勧めてくださるようお願いしたい。
| 項目 | 2002年度予算 | 02年度決算 | 03年度予算 |
| (収入) | |||
| 会費収入 | 650,000 | 699,000 | 870,000 |
| 拠出金 | 130,000 | ||
| 寄付 | 75,000 | ||
| 雑収入 | 4,969 | ||
| 収入計 | 650,000 | 908,969 | 870,000 |
| (支出) | |||
| ニューズ・レター編集費 | 100,000 | 100,000 | |
| 通信費 | 54,000 | 183,760 | 60,000 |
| 大会費用 | 50,000 | 63,620 | 50,000 |
| アルバイト料 | 90,000 | 35,000 | 90,000 |
| 年報発行準備費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 若手研究会費用 | 50,000 | ||
| 雑費 | 72,811 | 30,000 | |
| 支出計 | 394,000 | 455,191 | 480,000 |
| 来期繰越金 | 256,000 | 453,778 | 390,000 |
| ・予算での会員数は一般(122→150)、院生(26→40)を見込んでいる。 | |||
2003年度年次大会のテーマとして、私達は、日本の占領・戦後史を中心に「民主化」の問題を検討することにしました。
2002年12月、同時代史学会は、イラク戦争に向けて急速に展開する国際情勢のなかで、戦争と平和の同時代史的意義の検討から、その営みを開始しました。そのイラク戦争で米国ブッシュ政権は、「湾岸の民主化」を事実上の大義名分に掲げて戦争へと突き進み、日本・ドイツの「成功」経験や「湾岸民主化」論の可能性を語り続けました。このような今こそ、日本の占領史・戦後史を中核的に検討する集団として出発した同時代史学会に集う研究者と市民は、日本の占領・戦後史および比較占領・戦後史をふまえた批判と内省に基づく発言を求められているのではないでしょうか。
そこでまず午前のシンポジウム「地域における占領と民主化」では、近年、占領史研究のひとつの焦点となっている地域からみた占領史を、民主化に焦点をあて、さらに日本近代史の流れの中に位置づける観点から、大串潤児さん・荒木田岳さんの両氏に報告していただきます。そして深川美奈さん(ドイツ占領史)、荒敬さんからコメントをいただき、地域から見た戦後占領史の可能性を検討します。
次に午後のシンポジウム「占領とデモクラシー」では、加藤典洋さんに、戦後占領の「負の側面」がどのような世界経験としての可能性をもつかをめぐって所論を展開していただき、さらに古矢旬さんには、アメリカの対外戦争における民主化の論理とアメリカから見た日本の戦後デモクラシー像をめぐって語っていただきます。さらに安田浩さん、豊下楢彦さんからコメントをいただきます。
午前・午後のシンポジウムを通じて、日本の占領・戦後史の経験をめぐって今、同時代史学が何を発信し得るのか、発信すべきかについての活発な討論を期待したいと思います。会員の皆様には後日あらためてくわしい大会案内をお送りします。奮って御参集ください。
日時:2003年12月7日(日曜日) 午前9時30分受付開始(予定)
場所:法政大学市ケ谷校舎ボアソナード・タワー26階スカイホール
| 報告者 | 大串潤児 | 荒木田 岳 |
|---|---|---|
| コメンテーター | 深川美奈 | 荒 敬 |
| 報告者 | 加藤典洋 | 古矢 旬 |
|---|---|---|
| コメンテーター | 安田 浩 | 豊下楢彦 |
午後の最初に会員総会、午後のシンポジウム後に懇親会があります。
日時:10月25日(土) 午後2時~5時
場所:立教大学池袋キャンパス 7号館2階7203教室
報告:ジョン・プライス氏(カナダ・ビクトリア大学)
「E・H・ノーマンとサンフランシスコ講和」
連絡先:〒301-8555 竜ヶ崎市平畑120
流通経済大学法学部 植村秀樹研究室
事務局E-mail:y-ogura@mx6.ttcn.ne.jp(小倉裕児)
なお、占領・戦後史研究会の年末シンポは12月6日(土)です。
いま同時代史学会では、今年12月の第2回大会にむけて、テーマ調整や事務的準備などに力を注いでいます。ご案内にあるように、今年は「デモクラシーの同時代史」を掲げました。「デモクラシー」論は古くて新しいテーマですが、現在の情況と切り結ぶ形のテーマ設定を模索しています。それは現在「イラク占領」のモデルとして呼び出されている日本占領下の民主化という政治的文脈を遠景に置きながら、第1部では地域の実態に即して微視的に、第2部では日本占領下のデモクラシーそのものの巨視的評価を通して、この主題にアプローチするスタンスといえるかもしれません。そこは実態と記憶、政治と表象などがせめぎあう場であり、こうしたさまざまな次元のアンビヴァレンスの評価こそ、同時代史とは何かを考える基盤というべきかもしれません。多くの方々に参加していただき、活発な議論が展開されることを願っています。
ニューズレター第3号は、「若手研究会」2回分の報告・参加記を中心に、充実した内容を盛り込むことができました。またニューズレター編集担当としては、会員の皆様からの「投稿」をお願いしたいと思っています。現在も続いている「同時代史学会への期待と要望」以外にも、エッセイ・調査報告・書評・時評などさまざまなジャンルの文章が誌面を飾るようになれば、ニューズレターのバラエティも広がっていくはずです。当面締切は特になく、随時受け付けと考えています。こうしたニューズレターの充実とともに、学会誌(年報)の刊行がこの学会の大きな目標の一つなのですが、現在会員数は200名前後で、未だ目標値に届いていません。今号では、あらためて会員拡大の呼びかけを入れてありますが、ぜひお近くの関心のある方々へのお誘いをお願いしたいと思っています。(安田常雄)
同時代史学会のホームページが長谷川亮一さん(千葉大・院)の御協力でできました(http://jachs.hp.infoseek.co.jp/)。内容はこれからですが、研究会の案内、入会申込書、古いNewsLetterは、そちらで入手できます。ご利用ください。JACHSとは同時代史学会の英文表記です。(宮崎 章)
| 同時代史学会News Letter 第3号 |
|---|
| 発行日 2003年10月1日 |
| 同時代史学会 |
| 連絡先:〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1 |
| 東京大学大学院経済学研究科 伊藤正直研究室 |
| Tel 03-5841-5602 masaitoh@e.u-tokyo.ac.jp |